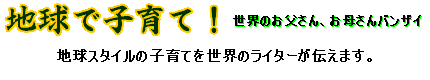子育てリポート
「見て見て! 赤ちゃんミミズを見つけたよ! お母さん、早く何か入れ物持ってきて!」
庭から息せき切って娘が家に走りこんでくる。小さなミミズ一匹に、まるで宝物を見つけたかのような興奮ぶりだ。彼女にとって別にミミズは珍しい存在ではない。そのへんの土を掘ればどこにでもいる。それでもミミズなどの虫の発見は、いつも彼女を有頂天にする。
そおっと触らなければつぶしてしまいそうな細さ、それでいて手の中で猛然と暴れる、強い生命力。キーウィ(ニュージーランド人のこと)・キッズは、庭のこんな小さな生物から、自分たち人間も属する自然の営みを学ぶ。
この国の多くの人々は一戸建てに住んでいる。自分の家のドアを開け一歩出れば、そこには庭が広がる。物理的には塀に囲まれている庭。しかし、考えようによっては、ニュージーランドの庭には"塀"などないことが、暮らすうちにわかってくる。
娘が友達の誕生日会によばれた時のこと。会のおしまいには、お返しとしてお菓子や小さなおもちゃが、招待された子どもたちに配られるが、その子のお返しは小さなかわいらしい花の鉢植えだった。それも大きな鉢にたくさん植わっている中から個々が好きなのを、小さな鉢に植え替え、持って帰るという趣向だった。
子どもたちは大喜び。どの子も「『マイ・ガーデン』に植えるんだ」と張り切って帰っていった。子ども用のガーデニンググッズや園芸本もあるほど、ニュージーランドにはガーデニング好きの子どもが多い。子どもたちはたいてい庭の一角に、自分専用のスペースを持っている。
そしてそこでお気に入りの花や野菜を育てる。種を植え、水をやり、肥料を与え、雑草を抜く。やがてそれは芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ。途中失敗して、枯らしてしまうこともあるだろう。植物はボタンひとつ押せば、一瞬のうちに花や実をつけるというものではない。
辛抱強く育てた野菜が実を結び、それを収穫、料理し、食卓を飾った時の誇らしい気持ち、また忘れずに水をやったおかげで、見事に咲いた花をお母さんにプレゼントする時のはずむ心。庭は子どもたちに喜びだけでなく、自信もプレゼントしてくれる。
しかし庭では常にプラスのエネルギーだけがあふれているわけではない。金魚など、自分が大切にしていたペットが死んでしまった時にも庭は重要な役割を果たす。泣きながら、「マイ・ガーデン」に穴を掘る。そしてそこに死んでしまった友達をそっと横たえる。お墓を作り、名前を書いてやる。そして大人に「金魚はどこへ行ったの?」と尋ねる。日々は過ぎても、時折そこに戻ってきて、小さな友達に、生きていた時と同じように声をかける。
もちろんペットだけではない。いつもはブーンと景気のいい羽音をたてて飛んでいるバンブルビー(マルハナバチ)が息絶え絶えで芝生に落ちているのを見るのも、昨日までひんやりとした影を作ってくれていたお気に入りの大木が風で倒れてしまったのを見るのも、ここ、庭なのだ。
遠くに行かずとも、家から一歩出ただけの庭で、自然界の一員としての掟を学ぶ。ここで育まれた知恵、良識、慈しみの心を持って、子どもたちは庭から一歩踏み出し、そしてどんどん歩き続ける。この国の庭には"塀"などない。ニュージーランドの庭は未来につながっている。
「開放日」と呼ばれる父兄参観の日、あれこれと指図して服従を強いる、常に眉間に皺を寄せている先生が私に言った。「子どもたちは家に帰ると、祖父母、両親、お手伝いさん、その他の大人に甘やかされ放題。だから幼稚園では厳しくする必要があるのです」。 1979年から始まった一人っ子政策により、家庭では自然と、一人の子どもにたくさんの保護者の注意が集まる。そして幼稚園には、「わが子にもっと漢字を教えてくれ」「もっと朗読の練習を」「英語にも力を入れて」といった、学習に重きをおいてほしいという強い要望が寄せられるという。 中国では、なぜこんなに早期教育に熱心なのだろうか。園長先生はどう思うかと聞いてみると、次のような答えが返ってきた。「深センに働きに出て来た両親は、内陸部の貧しい農村の暮らしがどんなものかを知っています。そして、そこから抜け出すためには教育が必要であると痛感しています。周りが皆始めており、次々と習得しているというのに、スタート地点からわが子を遅らせてはなるまいと、競争はどんどんヒートアップしていくのでしょう」。 25年という短い間に、広東省を代表する大都市に成長した深セン市では、「そこで何を教えてくれるのか」が、幼稚園はじめ、あらゆる事柄の選択重要項目になっているようである。 毎日JP 「世界の子育て」より転載 「いかにも幼稚園の先生らしい人」と言えば、日本では大概、やさしそうな雰囲気の人を思い浮かべるに違いない。しかし中国の幼稚園の先生は、腕組みをし、少し離れたところから、まるで監視しているかのごとく立ちはだかり、厳しくてコワイという印象だ。手洗いしかり、お遊戯の時間しかり、幼稚園児なのだから、そんなにきっちり決着つけなくとも、もうちょっとなごやかに、あるいは適当にできないものかと感じることしばしばである。
「いかにも幼稚園の先生らしい人」と言えば、日本では大概、やさしそうな雰囲気の人を思い浮かべるに違いない。しかし中国の幼稚園の先生は、腕組みをし、少し離れたところから、まるで監視しているかのごとく立ちはだかり、厳しくてコワイという印象だ。手洗いしかり、お遊戯の時間しかり、幼稚園児なのだから、そんなにきっちり決着つけなくとも、もうちょっとなごやかに、あるいは適当にできないものかと感じることしばしばである。
 中国でも核家族が増えてきてはいるものの、祖父母と同居している家庭が断然多い。私が暮らす深セン市は、中国で最も早く改革開放を実施したところで、経済躍進にともない、仕事を求めてたくさんの労働者が地方から集まっている場所だ。「移民の街」という異名を持つ深セン市の平均年齢は、なんと29才だそうで、地方から出てきた若者がこの街で結婚し、子どもが生まれると、赤ん坊や働く親の面倒を見るために、田舎から祖父母が出てきて同居する、というケースが多いようだ。
中国でも核家族が増えてきてはいるものの、祖父母と同居している家庭が断然多い。私が暮らす深セン市は、中国で最も早く改革開放を実施したところで、経済躍進にともない、仕事を求めてたくさんの労働者が地方から集まっている場所だ。「移民の街」という異名を持つ深セン市の平均年齢は、なんと29才だそうで、地方から出てきた若者がこの街で結婚し、子どもが生まれると、赤ん坊や働く親の面倒を見るために、田舎から祖父母が出てきて同居する、というケースが多いようだ。
"It's opened(子宮口が開いてます)!!"という私の叫び声に反応して、助産婦さんが駆け付けた。そして、足の間をのぞいて"Yes, it's opened(ホントだ、開いてますね)"と確認する。慌てて、無痛分娩の処置をお願いすると" too late(もう遅すぎです)"と首を横に振った。フィンランドでの初の出産と無痛分娩は、ライターとして、いつの日か記事を書くのに有用だろうと、たくましい野心を持っていた私は、「ノォオオオー!」と叫んだ。
なおも助産婦が"Push, push(いきんで)!"と指示を出す。頭がもう見えているそうだ。こうなったら、とっとと終わってくれ。私はすでに決めておいた我が子の名前を叫んだ。「ユーウーキぃー!」「オギャー!」夫の後日談によると、優樹の泣き声は、お腹の中からもう聞こえていたという。2月25日の22時。我が家の次男クンは226事件の一日前にやってきた。産みたてのほやほやを胸に抱き、そっと覗きこむと、その顔は5年前の海渡そのものであった。時間差双子――そんなものがこの世に存在するとすれば、この二人のことをいうのだろう。私たちは優樹のセカンドネームを「デジャブー」とつけることにした――ウソだ。
****
了
長きに渡って最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。読者の皆様からのご意見・ご感想などがございましたら、靴家さちこ(sapikow2003@yahoo.co.jp)まで、また「入院生活や乳児のお世話の仕方の違いなども、引き続き執筆してほしい!」などというリクエストがございましたら、サイト管理人の椰子ノ木やほいさん(yahoi@chikyumaru.net)までお寄せいただけますと幸いです。
北の果てより感謝をこめて/靴家さちこ
夜中の2時を過ぎ。私は身の回りの支度を整え、夫の運転でキャティロオピストを目指した。病院の産科のフロアにたどり着くと、部屋が空くまで待合室で待たされ、ほどなくしてお産待ちの部屋に通された。病院からパジャマとガウンを借りて、お腹の周りに胎児の心拍数を測る計測器が取り付けられ、私はベッドに横たわった。
お産はなかなか進まず、痛みもなかったので翌朝8時まで寝てしまった。夫は一睡もせず朝を迎えたらしい。昼間に回診に来た医師が、一度家に帰ってはどうかと言いかけると、夫がトンデモナイ、産みます!と私に代わって宣言した。ついに夕方回診に来た医師から、陣痛促進剤が処方され、分娩室へ移動。いよいよ......である。日本で陣痛促進剤を使った私の姉は、「すっごく痛かった」と言っていたので、私はもうどんなことになってしまうのやら、気が気でなかった。
が、それでもなかなか進まず、時刻は夜の8時。再び回診に来た医師が私との合意の元、人工破水の処置をした。このあと、痛みはすぐさま拡大した。「ねぇ、ちょっと、痛いんだけど」夫をつつくと、助産婦さんを呼んでくれた。この時の担当の助産婦さんは、二人とも若いのに英語がしゃべれないと言うので夫がカツを入れると、そのうち一人が単語と単語をつなぎ合わせて、英語で笑気ガスの使い方を説明してくれた。
鼻で吸って、口から吐く――これが結構、難しい。ちょっと考え事などをすると、すぐに逆をやってしまう。「効いてきたみたい。ありがとう」と助産婦さんに礼を言った。が、5分もすると痛みが増す。再び夫が呼びに行くと、「あらら」と器具をいじりながら助産婦さんが言う。なんと、ガスなど最初から全然出ていなかったのだ。「なんだ、効いていたような気がしてただけなのね、イテテテ」
そして、今度こそ、本格的にガスの吸引に取り組む。先ほどの医師が、無痛分娩を始めるにも、適度な痛みは必要なので十分痛くなってから声をかけるようにと言っていたので、十分痛いってどれくらいの痛さだろうと考えていると、鋭い痛みが下腹部を走り、私は、吸引マスクを放り投げた。床からマスクを拾い上げ、夫が私の顔を覗き込む。「痛いんだってば!」と叫ぶと、「そりゃ、痛いだろうよ。で、どうしてほしいの?」と諭しかけた夫の肩をぐいとひっつかんだ。つかんだ勢いで、私は半分夫によじのぼる。
――(子宮口が)開いている!――そう思い、とっさに叫んだ。"It's opened(開いてます)!!"
フィンランドでは3000グラム未満で生まれた新生児に対して、入院中に厳しい血糖値のチェックが入るという。予定日が迫りつつある中、私はお腹の子を3000グラム以上に産むべく、日々是怒涛のように食べて暮らしていた。
義姉は、「もう赤ちゃんが生まれる夢を見て、朝4時に起きたの。それで眠れなくなったものだから」と袋一杯のプッラ(菓子パン)を差し出した。それも、早速もぐもぐお茶で流し込むと、ただでさえ胎児に圧迫されている胃がパンパンに膨れ上がり、しゃっくりが出てきた。「これからサマーコテージに行くけど、まだ産まれないわよね」と言う義姉を送りだして「じゃあ、来週末に産まれてみる?」とお腹に語りかけると、中にいるヒトのやる気がわいてきたのか、お腹全体がピーンと固く張った。そして、その張りは、夕方以降に20分間隔で来るようになった。
夫と海渡と三人で寝る、キングサイズのベッドに横たわって、夫が本の読み聞かせを始めた頃。まだカチャカチャとケータイの時計を見てさりげなくお腹の収縮を計測している私に、「何やってんだ!」と夫のチェックが入る。「えーと、あの―、陣痛みたいな、そうでないみたいなものをちょっと......」としどろもどろに言うと、階下で静かに計測をするようにと促された。ほどなくして、寝付けなかった海渡を連れて、夫も階段を下りてくる。「それで、どうなんだ」「あの、あると言えばあるのだけど、もう引っ込んじゃったかも」実際に、お腹の収縮は、さっきまでは12分間隔で来ていたのに、今のところ20分過ぎてもまだやってこない。
3人連れだって寝室に戻ることを提案しようと思った矢先に、夫の口からこんな言葉がこぼれた。「陣痛が来て良かったよ。先週の会議で、上司からの仕事を断っただろ。これで近日中に生まれなかった日には、オフィスに居づらかったかも」――いくら根性の据わっている夫でも、さすがに無神経ではなかったのだ――これは、産まなくては。
海渡を寝かしつけ、夫から連絡を受けた義姉が息せき切って現れると、夫がおもむろに発言した。「変だと思われるかもしれないけど、僕もちょっと陣痛らしきものを感じている」そう言って、お腹に手をあてた。そんなアホな――と義姉を振り向くと、彼女もお腹をさすりながら「実は、私もよ」と苦笑する。一族郎党、陣痛祭り――私は観念した――もう、今日産むしかない。
フィンランドの保健センターの最後の健診の日。「日本でもう一人産んでいるんだから、同じことよ」と保健婦が微笑むと、夫が「ちょっと待った」をかけた。
「あなたは、あなた自身が外国に住んでいたことがあるというのに、そんなことも分からないのか! 日本とフィンランドの出産の違いは、昼と夜ほどの差がある。日本では自然分娩が主流で、お願いしてお願いしてやっと痛み止めの処置がしてもらえるんだ。うちの奥さんは、フィンランドで初めて無痛分娩を体験することになる。一人目と一緒だなんて、そんな気楽なことを言わないでほしいッ」
一気にまくしたてる夫に気押され、ぽかんと口を開けたままの保健婦を見やると、眼鏡の奥で、細くて小さな眼が――釣り上がっていた。「そんなに言うなら、事前に病院見学と医師との面談をお勧めします」といつものおとぎ話の声より2オクターブ低い声で言うと、保健婦は病院の連絡先が書いてあるメモを私に手渡した。
ちなみに、ケラヴァの近くで出産入院の設備がある病院は、キャティロオピストとナイステンクリニッカの2か所だけで、両方ともヘルシンキにある。ヘルシンキ在住の日本人友達に会うと、みんな口々に「出産はケラヴァの病院で?」と聞いてくる。それに対して私が「いや、ヘルシンキで」と答えると、皆一様に驚いた。当然だろう。私だって日本の感覚から言えば、埼玉に住んでいる人間がお産のため東京まで車でぶっ飛ばしてくるなんて、ちょっと考えられない。幸いケラヴァからでも、多く見積もって車で20分で行けるという。それでも、一応経産婦なので、車の中で頭が出ていたとかいう事態にならないように気をつけなくては!――「慌てないで、ゆっくりね」――私はお腹に語りかけた。
1月某日、夫もそこで生まれたという、キャティロオピストに電話して英語による院内見学ツアーについて問い合わせると、ツアーは2月の末に予定されているという。「スイマセン、予定日が3月3日なので、それでは遅すぎると思うんですが・・・・・・」と1月中、もしくは2月上旬の可能性を問うと「生憎、それほど多くの外国人の出産予定が見込まれていないため、ありません」とのこと。私はツアーに参加することは断念して、夫の付き添いのもとで医師との面談をし、病院の中をぶらぶら歩いた。
さて、そんなことをしているうちにエックスデーは刻一刻、と近づいてくる。私は、日本のように厳しい体重管理がないのをいいことに、夜中に一度は起き出してきてはラーメンをすすっていた。昼間はラーメンのみならず、天ぷらでもお鮨でもそれはもう、積極的に食べていた。ただ、これには理由がある。フィンランドでは3千グラム未満の新生児は、身体が小さめということで、病院での血糖値のチェックが厳しくなると聞いていたのだ。この段階での私の体重は、長男がお腹にいた頃と同じ10キロオーバー。長男は2960グラムで生まれてきた。予定日まであと1週間強。もっと食べなくては――私は、週末のランチに、ステーキ100グラムをおかわりした。
フィンランドでは、妊婦の検診は病院にではなく、テルヴェウスケスクス(保健センター)のネウヴォラ(相談所)に通う。家から車で5分とかからない保健センターでの私の担当の保健婦さんは、自身もアブダビに住んでいたことがあるという、やや年配の女性だった。「英語で話しましょうか、えええ、それともフィンランド語?」とゆったり話す様子が、話すというより昔話を読んでいるような感じ。「英語でお願いします」と答えながら吹き出しそうなのを堪えていた。
その後の検診は、出産までに月に1回、9か月に入って月に2回、臨月は毎週、と合計13回に渡って、尿検査、体重と血圧の測定、腹囲や子宮底の計測や、血液検査、血中ヘモグロビン量の計測が行われた。保健センターの医師による診察は、12週目、28週目と36週目にあり、超音波検査は、保健センターには設備がないため、北へ20キロほどのところにあるヒュビンカーの総合病院に自ら予約を取って出向けとのことだった。
余談だが、フィンランドでは、胎児の性別を教えたがらない医師が多い。さらに親としても、生まれてくるまで知らずに楽しみに取っておきたい、というフィンランド人が多い。知り合いのフィンランド人に、逆に何故知りたいのかと聞かれ、私が「名前を決めたり、育児用品を買い揃えたりするのに、性別が分からないと不都合」だと答えると、「へえー」と驚き半分、納得半分の顔をされた。
そんなわけで、ヒュビンカー総合病院での超音波検査では、先生をあてにすることなく自ら目を凝らして見ていたが、凝らすまでもなく、モニターに立派なモノが大写しに映っていた。担当の中年の医師は、英語は勘弁してという人だったので、夫にそのモノが何であるかを聞いてもらうと、もっと接写して「ああ、タマですね」と、いともあっさり認められた。
生まれてくる子が男の子であることがわかったところで、再び健康センターでの検診。例によって普通に話しているのに何もかもが「むかぁ~し、むかし」みたいな語調の保健婦に「男の子?それとも女の子?」と聞かれ「男の子です」と教えてあげると、腹囲を測った手を止め、「まぁ、それは楽しみね」だの、「息子さんは喜んだ?」だのと話を続ける。そして、あらゆる測定が終わったところで、椅子に座ると「あれ?」と首をかしげ、私の目をのぞきこむ。「あのぅ、私ぁ、何センチって言いましたかね?」――志村けんのけんバァさんか。数値の再確認をされたのは、これが初めてではなかった。
翌月の診察の日。駐車場からセンターの建物まで歩く途中、夫が言った。「きっと、今日も性別をきいてくると思うよ」私は、まさかぁ、と笑う。「賭けてもいい。5ユーロだ」と夫は引き下がらない。予言は的中し、保健婦は再び私の腹囲を測りながら胎児の性別を聞いた。夫は指をこすって"金払え"のジェスチャーをした。その後、「あとは産むばかり」という話になり「もう一人産んでるんだから、同じことよ」と微笑む保健婦に、夫が「ちょっと待った」をかけた。
日本で長男の出産中、痛みにもがき苦しむ私に、助産婦さんが筋肉弛緩剤を投与してくれた。この和痛の処置により、ほろ酔い気分で眠気が襲ってきた私は「あさにふんれもいいれすか(朝に産んでもいいですか)?」などとふざけたことを言い出す始末。「ダメです。今すぐいきんでください」すげなく助産婦さんに却下され、とりあえず、下半身に力を入れて踏ん張ってみることにした。
踏ん張ると、太腿がぶるぶる震え、火が付いたように熱くなった。すると――「いきみ、お上手ですよ」「そうですよ、ほら、すごい」「えらいですよ、その調子!」――要望通り、4人の助産婦さんが大声で口々に私をほめちぎってくれている。おお、快感!それでも、2回、3回目と踏ん張って出なかった時には、もう一生出てこないのかと泣きそうになった。そして4回目――両足の間に、バタバタと鯉のようなものが泳ぎ出てきた。泣いてはいなかったものの、慌てふためいて動揺しているのが感じ取れた。7月7日、七夕の日の午前5時。長男、海渡の誕生だった。
********
あれから約5年が経ち、一家で移住したフィンランドでの初夏のこと。意味もなく小腹が減るので、もしや、と思ったら、妊娠していた。ほどなくして、長男の時と同様、出血があり、慌ててかかりつけの医師がいるクリニックに電話すると、夏休み中で2週間先まで予約が取れないという。誰でもかまわないと食い下がったが、夏休み中で医師の数が少ないので、どのみち2週間先まで予約が取れないのだという。
「2週間!血が出ちゃってるのにですか!」と怒りを表明し、手が空いている医師を電話口に回してもらった。状況を説明すると、痛みを伴わない限り、出血の量がこれ以上多くならない限りは、特に問題がないだろうとのことだった。それに万が一、出血の量が増えたとしても――その場合には緊急で病院に来てもらうことになるが――もともと胎芽や胎児の発育が悪く、それゆえに流産するわけなので、今日明日の診察でどうにかできるものではない、という説明だった。
幸い出血はすぐに止まり、私は安静にゴロゴロして過ごした。今度の悪阻は、日本食を――特に"ラーメン"を食べると簡単に収まる。せっせとラーメンを食べている間に2週間はあっという間に過ぎ、クリニックの医師による診断で胎児の無事が確認された。これを持って正式に、海渡に「ママのお腹に赤ちゃんがいるよ」と発表した。「おいしゃさんが、ママのおなかにあかちゃんをいれてくれたんだね」と独自の想像力を働かせて目を輝かせる息子よ――その言葉の通りだとすると、お腹の赤ちゃんと君は異父兄弟になってしまう。が、その辺の細かい教育はまた後日にすることにしよう。
陣痛が来た――よりによって麻酔医のいない日曜日に。痛みが本格的になるまで待って、私達は夜中の2時に家を出た。タクシーを拾い、A病院を目指す。先に連絡を入れておいたので、受け入れはスムーズだった。が、担当の助産婦さんが、早速日本語で私だけにテキパキと話すので夫がストップをかける。"Do you speak English ?"間髪いれずに「ノー」と助産婦さん。「あの、スイマセン、わざわざ事前に紙に書いて、英語での対応をお願いしてあるんですけど。イテテテ」痛みを伴った私の怒り顔はなかなかの迫力だったに違いない。一陣の風となって、助産婦さんは走り去った。
――役所で、コンビニで、宝石店で、ありとあらゆる場所で夫がぶつけてきた"Do you speak English ?"に、悪びれもせず「ノー」と即答し、「すみません、お連れ様が通訳をしていただけますか?」と私をただ働きの通訳者として使ってきた英語非対応の日本人の面々が、走馬灯のように駆け巡る。その上、こんな人生の一大事の場面でも夫の通訳係をするのかと思うと、もう、ちゃぶ台でもひっくり返したい気分だった。
そして、やっと英語が堪能な助産婦さんが入ってきたところで、早速本題に入る。「あと何時間ぐらいで産まれそうですか?」「さぁ、あと5時間か7時間ぐらいはかかりそうですね」「今、もう月曜日ですよね。麻酔医さんは何時にいらっしゃるんですか?」「9時頃ですね。でも、もうその頃にはご出産なさっているはずです」ガーン。やっぱり私は"自然分娩"で産むのだ。この期に及んでまだ覚悟が固まらず、動揺する。
「無痛分娩できないの?」雰囲気を察して夫が口をはさむ。「イテテテ、麻酔医が朝9時にならないと来ないんだって」と身をよじりながら答えると、「おい、君ッ!なんとかならないのか!痛がっているじゃないか!」夫が、助産婦さんに食らいつく。「ですから、麻酔医が......」「そんなもんいなくったって、設備や薬はあるだろう。君がなんとかできないのか!」「本人がどうしても必要だと言っているんですか?ご主人の意に従って処方するものではありませんよ!」――助産婦さんも負けてはいない。「イテテテ。あの、何でもいいですから、何か処方していただけますか?」慌てて間に入った。
ほどなくして、助産婦さんが筋肉弛緩剤を投与してくれた。これは、和痛の処置であって、波のように交互でやってくる痛みと痛みの軽い期間のうち、痛みの軽い期間中に体がリラックスする効果を増大させるものだという。――これが、利いた。「イテー、もうダメ、イテテー」と叫んだかと思うと、その次にはほろ酔い気分が気持ちいい。と同時に、眠気も襲ってきた。胎児用モニターを覗き込んで、助産婦さんが眉をひそめる。「すみません。赤ちゃんが寝てしまいそうなので、もういきんでください」「ふみまふぇん、わらひもねむひんれふけろ、はさにふんれもいいれふか(すみません、私も眠いんですけど、朝に産んでもいいですか)?」
日本在住のアメリカ人女性が主催する外国人向けの両親学級にて。在住外国人の間で、日本で主流の自然分娩がやり玉にあげられた。自身が日本で出産を経験している主催者は、自らの経験から「必ずしもみんながみんな自然分娩を強要されるわけではなく、実際にはさまざまな対応が可能なはず。前もって病院側に希望する出産スタイルを紙に書くなどして伝えておいた方がいい」と熱く勧めた。
そこで、家に帰ってから夫と頭をつきあわせて、お産に関する病院への要求を書き出してみた。
1)痛みに弱いので、無痛、和痛、いかなる処置でも構わないので、できるかぎりで対応してほしい。
2)立会いをする夫が外国人なので、英語での対応をお願いしたい。
3)怒られると委縮し、褒められるとがんばれるタイプなので、どんな些細なことでも大げさに褒めてほしい。
最初の二つはいいとして、三番目は過保護な親の通信簿の記入欄か。一瞬消そうかと思ったが、万が一、自然分娩となった日には褒め言葉は絶対必須だと思い、書き残した。
そして、いよいよ38週目の最後の検診。そこで、私は許容体重ギリギリまで来てしまい、助産婦さんから「これ以上、増やさないで」ときつくお叱りをいただいた。――それでは、今日から断食しろと?と頭で反撃しながらも、この段階に至っても食い悪阻が治まらず、おせんべいが手放せない。それどころか、これから出産してしまうと、赤ちゃん連れでは外食もままならず、じっくり手の込んだ料理もできないに違いない――と思ったので、回転寿司やらイタリアンやらと行っておきたい店には行き納めをし、家でも盛んに料理して――実によく食べた。
かくして日曜日の朝に――陣痛らしきものが、穏やかにやってきた。病院に電話を入れると、痛みの間隔に注意していよいよ陣痛らしくなったら来るように――とのことだった。「あのさ、今日、日曜日だよね」「予定日まだだよね」――お腹をさすりながら語りかける。週末だと麻酔医がいないのだ――。初産は時間がかかるものらしく、人によっては日付を越えることもあるという。――月曜の朝イチなら麻酔医が来るかしら――この期に及んでも、まだ無痛分娩があきらめきれない。
私は頭から布団をかぶって不貞寝をしてしまった。昼間に起きると、夫に外に連れ出された。臨月の妊婦に適度な運動は必要だと、勝手に専属コーチを名乗り出て方々を歩かせてきた夫は、こんな日でも鬼コーチだった。
母親学級で配られたプリントの<無痛分娩>の項目に、「日曜の夜は当直の麻酔医がいないため、無痛分娩の処置はいたしかねます」と書いてあるのを見つけた私は、「これは本当に、本当なんですか?」と食い入った。すると、「どうしても無痛分娩をなさりたいんですか?」と助産婦さん。「夫が、日本では無痛分娩の技術がないのだろうといぶかしがっております」と食い下がると「ご主人が外国の方だと、そうやって甘えてしまうお母さんが多いんですよね」とため息をつかれた。
――甘えるぅ?甘えているだとぉおおお!?――確かに、お腹の赤ちゃんの為ならどんな痛みも耐えようと思わない私は未熟かもしれない。が実際に、お金を払って医療行為を受けようというのに、病院のポリシーが優先で、患者が甘えん坊呼ばわりされるのはどういうことだ。見かねて妊婦友達が病院を変えることを勧めてくれたが、今さらそんなこと面倒くさくてやってられない。――そうだ。要は、週末に産まなければいいのだ。その日から、私はお腹の子に語りかけ始めた。「平日に生まれなさい。それから、あんまり痛くしないように」と。
病院から紹介された外国人向けの両親学級というのにも、夫とともに参加した。主催者は、日本で2人の子どもを産んだアメリカ人女性で、快活なジョークを交えながら、日本での出産話を盛り上げる。ビデオが上映され、見てみると、農家の大家族の嫁が、生まれてくる赤ちゃんのお兄ちゃん、お姉ちゃんも含む一族郎党が見守る中で、ひいひい叫びながら産んでいる――それだけ日本の出産はナチュラルなのです、と締めくくるビデオを見終わる頃には、私は固まっていた。慌てて隣を見ると、「僕はこんなにたくさんオーディエンスは要らないな」と早速夫が誤解している。一方近くの席のオランダ人夫婦は「日本でも家で産めるの?」と目を輝かせている。オランダでは、自宅出産が一般的なのだそうだ。
参加者の間で話題に上ったのは、無痛分娩のことであった。どちら様も、あちこちの産院で自然分娩を勧められているらしい。その理由は、日本では、麻酔医の確保が難しいとのことであった。そして何よりも、胎児や母体への麻酔による悪影響の恐れが無い、自然分娩が王道とされており、「痛い思いをして産んだからこそ可愛いいのだ」と、"痛み"は母になるための通過儀礼という文化的な要素も強い。じゃあ、鼻から痛い思いしてスイカを出せば、スイカが無性に可愛くなるのか?――そんなことは誰も言ってない。
日本では、妊婦さんの為に、ご存じ「母親学級」なるものがある。区でも開催されていたそうだが、私は通院しているA病院が主催するものに参加した。4回に渡って行われたそれは、私のようなへその曲がった人間にはやや息苦しい、健全な空気が漂うものであった。――第一回目は、母体と胎児のための食事や体重管理について。細かい栄養素別の表は、苦手だった家庭科の時間を彷彿させた。
第二回目は出産の具体的な経過について。陣痛が始まってから、お腹の中の我が子にご対面するまでのプロセスを学んだ。そこで私は、夫の国、フィンランドでなら当たり前の無痛分娩について聞いてみた。痛み恐怖症の小心者ゆえに、無痛分娩には興味シンシンだったのだ。ところが――助産婦さんは非常に困った顔をして、「胎児にとっても母体にとっても自然なお産の方が・」「麻酔による悪影響のリスクがあります」となんだかんだと言って自然分娩を薦める。――なんで無痛分娩をそんなに嫌がるかなぁ?
家に帰って病院のパンフレットを読み直して合点が行った。「自然分娩と母乳育児」――これこそがA病院のポリシーであり、無痛分娩がしたかったら、あらかじめそれを専門とする病院を選んでおくべきだったのである。――無痛、和痛、水中、アロマテラピーに食事はフレンチ――出産一つにも病院ごとにこんな多様なスタイルやポリシーがあるなんて――私のように、ただ近くで普通に用事だけを済ませたいナマケモノにとって、日本の選択肢の多さは、ただただ面倒くさくありがた迷惑だった。
第三回目は、「お乳の手入れ」がテーマ。産後の乳の出が良くなるように、安定期に入ってからのマッサージが薦められ、布製のおっぱいの模型を相手にやってみる。灰色の古ストッキングで作られた、血色の悪い乳首をいじくりまわすこの作業に、私も顔色を悪くし、さらに家でお風呂上がりに実践してみたが、なんだか滑稽で泣けてきた。私は、自分自身がほとんどミルク育ちで、それでも五体満足なので、母乳に対する意識は低かったのだ。
第四回目は、質疑応答のコーナーとなっていたが、もはや臨月の私達は、出産の痛みへの恐怖に、産前ブルーになっており、挙がる手もまばらだった。最後に小児科の先生から、赤ちゃんの発達についてありがたいレクチャーをいただいて解散。と思ったら、ちょっとまてぇー。私は、再び助産婦さんを捕まえた。配られたプリントの、「無痛分娩について」の項目に、「日曜の夜は当直の麻酔医がいないため、無痛分娩の処置はいたしかねます」と書いてあるのを見つけたからだ。
あれは今は昔、日本滞在時のこと――妊娠5ヶ月目して、健診の際にはフィンランド人の夫も病院についてくるようになった。
まず、日本の病院といえば、待ち時間が長い。そのことを重々承知している病院では、受付を済ませる際に、呼び出し用の小型の電子機器のようなものを持たせてくれた――にも関わらず、人口520万人の国出身の夫ときたら、順番待ちの素人だ。私が、本を一冊持って行くことを勧めたのにもかかわらず手ぶらで来てしまった彼は、妊婦さんの付き添いで来ているお母様方を目にしては「あの歳で出産はきついんじゃないの」だの「まさかあの人も妊婦じゃないよね」と、耳打ちしては、文庫本に目を落とす私の邪魔をする。「静かにして」と怒りつけて黙らせたものの、後日、フィンランドの健康センターや産院に通うようになってから、夫が目にしていたものとの違いをはっきり認識した――妊婦の付き添いは妊婦の夫であって、母親連れなど珍しいのだ――フィンランドでは。
それはさておき、出産時に夫が立ち会うことを前提に、英語環境が強そうな"広尾"という立地条件だけにこだわって決めたA病院であったが、実際に、医師が率先して夫に英語で話しかけてくれるということはほとんど無かった。これまでの経験で、同じく広尾の別の病院でもお医者さんともあろうお方が、風邪の所見一つを英語で言えないのを目の当たりにしたことがあったので、さほど驚きはしなかったし、日本に住んでいながら日本語ができない夫のほうが問題視されるのはいたしかたないとも思った。が、せっかく出産に立ち会ってくれようと張り切っている夫が言葉の壁に阻止されているのは切なく、言葉ごときの問題で日本の医療関係者のレベルが夫に怪しまれるのも、日本人としてはもどかしかった。
さらに超音波検査では、お腹の中の胎児のエコー写真を撮るわけだが、この写真にものすごい気合いを入れてらっしゃる先生が多いのには驚く。「あ、今ちょうどこっちを向きました」「あああ、お尻を向けて寝てしまっていますね・・・・・・」と、お腹に当てた機械にぐっと力を入れて、角度を変えてシャッターチャンスを狙う様子などは、本職はカメラマンかと思うような勢いだ。フィンランドでは、その辺も非常にあっさりしており、画像をモニターで一緒に見るだけで、写真がもらえなかったこともあった。というわけで、日本での長男の超音波写真は薄いアルバム一冊分ぐらいたまったが、フィンランド産の次男については5本の指が余るほどしかない。――許せ、次男坊。
我が家には、日本産の男の子が一人と、フィンランド産の男の子が一人いる。産まれる前にフィンランドに渡る可能性が出てきた長男には、彼の運命をそのままに「海を渡る=海渡(かいと)」と命名し、在住4年目にしてフィンランドで授かった次男には、フィンランドの白樺の木をイメージして「優しい樹=優樹(ゆうき)」と名付けた。この二人がこの世に登場した時のことを振り返って、日本とフィンランドの出産事情を比べてみよう。
長男を身ごもったのは2002年の晩秋。まだ日本に住んでいた時のことだった。早速、近くの産婦人科をネットで調べ、アットホームな小さめのクリニックを選んで出かけてみると、優秀そうな若い女の先生が、テキパキと診断を済ませてくれた。妊娠が確定されたものの、まだ12週で胎児が小さく、心拍数が確認できないので一週間後に再診してもらうことになった。ところが――その日を待たずして、ある朝下着に出血の跡を確認した私は、泣きながらクリニックに駆けつけた。胎児の生息は確認できたものの、切迫流産の可能性があるとのことで、私は、絶対安静を申し渡され、夜中でも何かあったらすぐ連絡するようにと、先生の携帯の番号が書かれたメモを渡された。
こんなに良い先生が見つかって、と安堵の涙をハンカチで押えていると、先生が「でも、そろそろ産院を確定した方がいいですね」などとおっしゃる。知人友人の間では比較的結婚が早く、妊娠、出産に関して知識が乏しかった私は、このクリニックのような「婦人科」では検診ができても、実際に産むためには「産科」、「産婦人科」がある病院にかかるものだとは知らなかったのだ。その場で先生からお薦めの病院を――出産に夫が立ち会うことも考えて、英語での対応が可能そうなところを――聞いたところ、A病院の名前が挙げられた。
早速先生に紹介状を書いてもらい、それを持って、A病院への検診通いが始まった。5ヶ月目に入って順調にせり出してきたお腹に、時期が近付いてきたことを感じてか、夫も病院についてくるようになった。
その夫が、これまでフィンランドで仕入れてきた知識を総合させると、30週目まで月に1回、それ以降は月に2回という、日本の病院での内診及び超音波検査の数は「多すぎ」だと言う。私としては、特に初期に出血騒ぎがあったので、胎児の無事を確認することができるのであれば、何度診てもらおうと構わなかったが、夫は、「電磁波が怖くないのか」「胎児をそっとしておいてあげたらいいのに」とあまり喜ばしく思っていない様子。早くも文化の違いを感じた。かくしてこの日を境に、私は日・フィン産み比べエキスパートへの道を歩むことになった――ウソだ。
3歳になる息子の通う保育園は、目黒・世田谷・渋谷どこからも近く、車での送り迎えも許可されていて便利だが、平凡な東京都内の認可保育園。園児の生活も日本の文化や生活習慣をベースにしている。お正月のお餅つきや豆まき、ひな祭りなどの行事があり、おやつにおにぎりが出る。
子供も親も先生も日本語でコミュニケーションし、日本ならではの保育園ライフを送っているのだが、ここには、両親のどちらかが外国人という園児が何人もいる。また、海外から転勤で日本に来ている駐在家族など、一時滞在の外国人家族の子供たちも結構いる。
日本に定住している人々で、家族のうち誰かが日本人ではないことはもう珍しくない。厚生労働省の調査でも、息子と同じ2006年生まれの日本の新生児で、親のいずれかが外国人の割合は30人に1人という。日本の多様化は進んでいるのだ。それでも「ハーフ」「ミックス」「帰国子女」「在日外国人」など、様々な枠はいまだに存在する。日本人の両親を持ち、日本で生まれ育ち、日本語で教育を受け、日本だけで暮らす、それらすべてを満たさない場合、「何かが違う」と周囲に受け取られたりする風潮は、まだある。
しかし、今こうして息子の保育園を見ると、日本がようやく多様化を受け入れはじめたのを感じる。私の子供時代よりはマシということか。当時、両親のいずれかまたは両方が日本人でない、日本で育っていない、日本語で教育を受けていない、将来日本で暮らすかどうかわからない、そういうわが子を「日本の普通の保育園」に入れても大丈夫かな、と昔の親たちは慎重にならざるをえなかった。私自身も多様性に不寛容な日本を何度も目撃し、経験した。
昔との違いを最も感じるのは、仕事の都合で一時滞在するだけの外国人家族がわざわざ日本の保育園を選ぶこと。こうした家族は、数年でまた日本を離れてしまうし、インターナショナルスクールや母国の教育システムを持つ都内の保育園・幼稚園もあるのに、日本の保育園を選択しているわけだ。逆に考えれば、日本人の海外転勤族が、子供を現地校に通わせるのと同じかな。居住地のライフスタイルを経験するのだ。
小さな息子にとって、保育園という日常の中でお友達を通して多様性に触れることができるのはいいことだと思う。まだわからないかもしれないけれど、広い世の中にあるもっといろいろな民族や言語、それぞれ違うライフスタイルがあることを知るきっかけを感じてほしい。人間の多様性の素晴らしさについて、全部違っているけど全部いいんだよ、って少しずつ話していきたいと思う。
息子は、3歳から6歳前まで、デンマーク発祥の森の幼稚園に通った。そこにはおもちゃも園舎もなく、晴れの日も雨の日も風の日も雪の日も、毎日朝8時半から4時半まで森で過ごした。四季を通じて日々変化する森の木々や草花、きのこ、虫たちや小動物、そして落ちている木の枝や石ころ、水たまりが遊び相手。それまで息子は、冬場は風邪をひくことが多かったが、森の幼稚園に行き始めて、目に見えて強く、たくましくなり、病欠もほとんどなかった。
そんな彼も、昨年8月から0年生として学校に通い始めた。放課後は夕方まで、学童クラブで過ごしているせいか、息子は突然「室内遊び」に目覚めた。これまでほとんど興味を示さなかったレゴを手始めに、Yu-Gi-Oh!などのカードゲームに熱中、ついにはプレステ、Wiiの虜となった。毎日の食卓での話題と言えばレゴ・スターウォーズのゲームで今日はどのステージまで行けた、というようなことばかりで、このまま「バーチャルワールド」の住人になってしまうのか、と少し不安になった。
先日、息子と愛犬ポルカを連れて自宅近くの小川沿いを散歩していたときのこと。突然、ポルカが興奮した様子で小川に飛び込んだ。そこにはカモがいて必死に逃れようとしたのも束の間、元々猟犬であるポルカは、あっという間にカモを口にくわえて土手に戻ってきた。ほとんど瀕死の状態だった。シカや野うさぎ、キジを夫とともに家に持って帰って食べた経験のある私だが、これにはさすがにショックを受け、カモを前に立ちすくんでいた。すると、すかさず息子が「まだ完全に死んでいないみたいだから、石で頭を叩いて楽にしてあげたほうがいいよね?」と言った。もう助からないのだから、早く死なせてあげた方がよい、ということを、息子は知っていたし、冷静だった。
ちょうど夫が様子を見に来た。カモを家に持って帰って食べようということになった。私はふと、息子に「びっくりしなかったの?」と聞いた。彼は「少しびっくりしたけど、家で大事に食べてあげれば、きっとカモさんもそれほど悲しまないよ」と言った。そして、「ママ、忘れたの?僕にはバイキングの血が半分流れているんだよ」とウインクして犬と一緒にわが家へ走って行った。
東京や横浜といった都会暮らしから、デンマークの田舎町へ移り住んで、もうすぐ7年が経とうとしている。より自然に寄り添った暮らしに慣れてきたつもりでも、まだまだハッとさせられるような出来事に多く遭遇する。
ゲームに夢中になってばかりいると思っていた6歳の息子のとっさの行動に、自然との関わり方がしっかり身に付いてきていると感じられ、少し頼もしく思った。
≪ニールセン北村朋子/プロフィール≫
デンマーク・ロラン島在住のライター、ジャーナリスト、コーディネーター。再生可能エネルギーの利用等の環境や食など、地球と人にうれしいライフスタイル追求がライフワーク。小学0年生(6歳)の男児の母。森の幼稚園の運営委員の経験を活かし、子供が家族や社会、自然と関わりながら、子供らしく生きられる環境について考える日々。ロラン市地域活性化委員、デンマーク・インターナショナル・プレスセンター・メディア代表メンバー。
こちらの学校は、父兄の奉仕活動(ボランティア)によって支えられる。学校行事の準備や主催はもちろん、スポーツチームのコーチを親が引き受ける。実際に授業に入って先生の手伝いをすることまである。パパも大活躍。
フルタイムで働く父兄は、昼休み時間や有給取得により奉仕活動に参加しているようだ。
子どもが通う幼稚園から中学までの私立の一貫校では、1年に20時間のボランティア活動参加が義務付けられており、達成しないと罰金になる。実際に参加する前に、指紋登録、肺結核の検査、インターネット上で子ども虐待に関するクラスを取得しなくてはならない。
私は週に数回、昼休みの監視係をしている。幼稚園から小学校低学年の子どもが、ちゃんと座って昼食をとるように見守る。その後、子どもが校庭で安全に遊んでいるかを監視する役目だ。お弁当箱を開けたり、飲み物の蓋を取ったり。そして子どもと一緒にブランコに乗って、砂場でお城を作ったりしていると、あっという間に活動の1時間が終わる。
一般的に親の奉仕活動への参加度が高い学校は、優良校だといわれている。親には負担ではあるが、学校での子どもの様子を見る機会が増えるという利点ではある。
【朝日小学生新聞「朝日おかあさん新聞」掲載】
現在、世界でも一、二を争う程、少子化が進んでいる韓国。2005年に女性が生涯に産む子どもの数を表す出生率が1.08にまで落ち込み、その後、2007年には1.26に回復をしたものの、依然として少子化に歯止めがかかっているという状況ではない。
韓国でも、都市部では核家族化が進み、一家庭に於ける子どもの人数は1人、即ち一人っ子の家庭が目立つ。韓国で何故、日本以上の少子化が猛スピードで進んでいるのかを考えてみたい。
日本でも韓国の教育事情については度々、マスコミでも取り上げられ、詳しくは知らなくとも、「韓国=教育熱心」という印象を持っている人も多いのではないだろうか?特に、最近では幼児期からの早期教育を重要視する傾向が高まっている。例えば、英語教育や、韓国の国語に当たるハングルの読み書きや計算の小学校入学前までの習得。また、各幼稚園や保育園でも保護者にいかに園のプログラムが優れているかをアピールすることに試行錯誤している。
また、小学校就学前の幼児を対象とした英語塾や学習塾の生徒の獲得合戦も過熱気味である。このようなことから、韓国で子ども一人当たりにかける一月の教育費は中産層の家庭で100万ウォン(日本円で10万円)に相当するという試算も出ている。これでは、子どもを一人当たり成人まで育て上げるのも、親の負担は非常に大きなものとなり、子どもを一人以上産むことを考えざるを得ないというのが親の本音なのだ。
儒教の影響が現在でも残る韓国では、「学を究めることこそ、将来が約束される」という考えが「学歴至上主義」につながっていると言える。日本でも教育への関心は高いという点では同じだが、韓国では部活動が盛んに行われる環境がなく、日本のように勉学以外のスポーツや技術などの分野でも打ち込める環境が少なからずあるというのが韓国との差である。単に大学に進学するためだけの勉強ではなく、様々な人に門戸を開き、学べる環境を整えていかないことには、韓国の少子化と教育の質の低下は避けられないのではないだろうか。
子どもの成長過程でさまざまなお祝い事や行事があるのはネパールも同じだが、カトマンズ盆地土着のネワール族の女性は一生に3度結婚するといわれ、大変珍しい結婚の儀式を行う。
旧市街のレンガ造りの建物に囲まれた広場に、赤い衣装にきらびやかな金の装飾品を身につけ、お化粧をした5歳から10歳頃の女の子たちが集合していた。この日は初めての結婚「イー」の日。お相手は不死身とされる果実マルメロの実の一種で、将来未亡人になることがないようにという意味があるそうだ。朝から司祭によって祈祷が執り行われ、女の子たちは縁起物のほら貝、牛乳、お香、米、染めた綿糸などの前に座り、一連の儀式は3日間にわたることもある。
いよいよ3度目が本当の人生の伴侶との結婚だ。果実や太陽は神の象徴で、嫁ぐ娘の健やかな成長と幸せの願いが込められた人生儀礼の伝統が今も変わることなく受け継がれている。
フィンランドの小学校では、子ども達が親の職場にやってきて、親の仕事を視察する、子ども達による職場参観というものがある。ある女子生徒はそのプロジェクトを通して、主婦である自分の母親が、いかに素晴らしい"家事のプロ"であるかを誇らしげにレポートにまとめた。女性の就業率が70%のこの国で、"主婦による家事仕事"ほど軽視されがちなものはない。家事は家族で分担し、お母さんも働いて高い税金を納めることが期待されている高福祉社会というお国柄ゆえ、なおさらだ。彼女の母親同様に、家では家事仕事もする担任の先生にとって、これは、まさしく目からウロコの体験だったという。「ただの家事仕事が、こんなにも尊敬に値するものだと知って、嬉しくなったわ」とにっこり微笑んだ。
また、ある男子生徒はレストランのウェイターである父親について、彼がいかに有能なウェイターであるかをクラス全員の前でとくとくとプレゼンテーションした。フィンランドでは、ウェイターという職種は、学歴と収入の低さを物語るもの。が、子どもの目を通せば「職業に貴賎なし」。一生懸命働いているパパやママはどんな仕事をしていても輝いて見えるのだ。
子ども達に仕事の尊さを教えるのが目的のこのプロジェクトを通して、いろんなことを学んでいるのはむしろ先生達の方であるらしい。
【朝日小学生新聞「朝日おかあさん新聞」掲載】
フランスでは、親が子どもにあくまで真実を語ろうとする、その真摯な、でもちょっと「?」な姿勢に驚かされることがある。
たとえば、親が子どもに離婚の理由から経過まで詳細にわたって打ち明けるので、まだ舌足らずな子どもの口から「家庭裁判所」やら「調停」、「弁護士」などという単語が飛び出し、啞然としたことがある。
養子縁組みをするカップルも多いが、まだ、ほんの乳飲み子に「あんたのね、本当のお母さんは南米のコロンビアっていうところに住んでいるんだよ。でもね、お母さんは貧しくてあんたを育てられない、だから、私たちが代わりに引き取ったんだよ、おーよしよし」などと、四六時中、執拗に説明している。
この「言葉のもつ魔術」は、とくに母子の間で深く信仰されているようだ。「子どもは知らなくてもいいことって、あるんじゃない?」なんて言おうものなら、すかさずバッシングされる。「重大でショッキングなことこそ、隠さないで、子どもがわかろうとわからまいと言わなくてはいけないのよ。口に出していうことで、私も、問題を客体化できる。そして、子どもも『そんなに大したことじゃないのかもしれないな』って思えるようになるの」と。
小児心理の権威として、フランスのママンたちの絶対的支持を得て読み継がれているドルトー氏の著書によれば、夜泣きをする、食欲不振などの症状をもつ赤ちゃんの多くが、この「話せばわかる」術で快方にむかうそうだ。
【朝日小学生新聞「朝日おかあさん新聞」掲載】
カナダでは給食がある学校は少ない。我が家の子どもたちの通う小学校にも給食はなく、毎日お弁当だ。だから子どもが就学年齢になってからの頭痛の種はランチ(お弁当)だ。特に息子より大きな子どものいる日本人の友人から、おにぎりを持参させたら友達にからかわれたと聞いたために、何を持たせたらいいのかと困ってしまった。
本人に希望を聞いたら、「サンドイッチがいい」と言う。とりあえずパンの種類や中身を変え、ラップタイプにしたら翌日は食パンのサンドイッチと工夫していた。
そんなある日、「カイル君は毎日、巻き寿司だよ。僕もお寿司が食べたい」と言い出した。カイル君のお母さんは日本人だ。
ランチといえばサンドイッチというのは一昔前のお話のようで、バンクーバーあたりの今どきのお弁当はバラエティ豊かだ。パスタやピザ、具がいっぱいのデラックスサラダにスープ、あるいは炒飯とおかず、インド系はサモサなど。高学年になると教室に電子レンジがあるので、温めて食べる料理が人気らしい。
昼休みに作りたてのお弁当を届ける保護者もいる。しかし、マクドナルドの袋を持って小学校を訪れる保護者を見たときには驚いた。移民の国、カナダではランチも多国籍、多様だ。
【朝日小学生新聞「朝日おかあさん新聞」掲載】
年に一度、小学校からハイスクールに至るまで、各学校では、「タレントショー」と呼ばれる行事が催される。楽器演奏、手品、コメディ、ダンス、芝居、歌などジャンルを問わず、「ぼく、わたしにはこんな才能があります」という何かがあれば誰でも参加できる。
学校行事とはいうものの、教育的な内容の必要はなく、ロックありヒップホップありと寛大だ。個人でもグループ参加でもかまわない。「これはスゴイ!」というものから、「これってほんとに才能って言える?」というお笑いものまで、子どもたちは大観衆を前に、スター気取りで見せる、聴かせる、うならせる。
今ではハイスクールに通う、将来ミュージシャン志望の我が息子も小学校時代から毎年、自分の"才能"をひけらかしている。「能ある鷹は爪を隠す」という言葉を知らないらしい。
何しろ、各ハイスクールの優勝者が、学校代表として競う郡のタレントショーともなると、スポンサーから優勝者に500ドル、優勝者を輩出した学校に2万ドルの賞金が授与されるのだから、爪を隠している場合ではない。学校にとっても、優れた才能のある子どもは"金のたまご"と化す。
ひょっとすると、将来世界に名をとどろかせるようなスーパースターも、こうした機会から花開くのかもしれない。
【朝日小学生新聞「朝日おかあさん新聞」掲載】
我が家の子どもたちは、南太平洋に浮かぶ小国サモアの公立学校に4年間通った。そのおおらかさは、日本とは対照的と言えた。ニュージーランドの教育システムに準じ、教育にはそれなりに力を入れているとはいうものの、途上国ゆえ教科書をはじめ教材はないに等しい。しかし、ないがゆえの工夫を見た。
たとえば「数の勉強をするから、棒を持っていらっしゃい」と先生がおっしゃれば、子どもたちは庭で拾い集めた小枝をたくさん抱えて登校。南の島の"数え棒"だ。
音楽の時間に活躍する"楽器"は、バケツをひっくり返して叩く"たいこ"で、このリズムに合わせ、子どもたちは手拍子を打ちながら見事な合唱を聴かせてくれた。サモア流音楽の授業だ。
こうした、先生方のアイデアであるものを工夫し教材にしてしまう術にはひたすら感心した。また、教材に頼れない分、子どもたちは必死に先生の言葉に耳を傾け、ノートを取る。そのノートが個々の教科書となるからだ。
その様子を眺めながら、恵まれすぎもよくないかも?と思いかけたころ、子どもたちのノートを覗くと、まちがって習っていることも発見。「う~ん。先生も人間だからたまにはまちがう......」ってことにしておこう。
【朝日小学生新聞「朝日おかあさん新聞」掲載】
「お母さん、この手紙にサインしてね」アメリカの公立学校にお世話になっている我が家の子どもたちは、学校で事あるごとに、保護者の許諾サインを求めてくる。サインを提出しないと、せっかくの楽しそうな学校行事に参加できないからだ。
日本で暮らしている頃は、遠足、キャンプ、性教育の授業など、学校教育の一環で行われる行事や活動に参加するのは当然だと思っていた。しかし、ここでは、どんな行事や活動も、保護者が主体となりその都度、参加、不参加を決める。不参加を決めたとしても、参加しないことで子どもたちが不利益を受けることはない。その場合、学校は、ちゃんと別の授業を用意してくれるからだ。
よくよく、考えてみれば、異なる人種が集うアメリカの学校において、それぞれの文化や宗教などあらゆる背景の違いを尊重するためには、こうした配慮は不可欠なのだろう。当初、内容を確かめもせず、サインの大安売りをしていた私は、いちいちお伺いを立てられるのも面倒だと思ったものだが、我が子が関わる行事や活動を保護者としてきっちり把握し、それが必要、妥当かを考えてみることは悪くない。
サインをする度、子どもたちに「与えるもの」「与えること」の責任は、保護者が持つのだということを意識させられる。
【朝日小学生新聞「朝日おかあさん新聞」掲載】
我が家の四人の子どもたちは、南太平洋に浮かぶサモアという小さな国の学校に四年間通った。ポリネシアの文化を色濃く残すこの国では小さな頃から助け合うことや分かち合うことはとても大切なことだと教えられる。
たとえばモノについても「有る人が無い人に貸す」「無い人は有る人から借りる」というのは自然なこと。そんな背景もあり、サモアでの貸し借りにまつわるエピソードは数えきれない。
ランチタイムのお弁当は、忘れた子もご馳走の子も持って来る気のない子もいっしょになって、そこにいる友だちと、そこにあるお弁当を分け合い、つまみ合い食べていた。
小銭のある子が飲み物を買えば、損得なんてセコイことは言わず居合わせた者みんなで回し飲みをしていた。(衛生的に云々はあっちに置いといて)定規を忘れた息子に自分の定規を折ってまで貸してくれた友だち(モノを大切にすることより貸すこと優先らしい)もいた。
「目の悪い子に君のメガネを貸してあげなさい」とおっしゃる先生の発言には、思わず「ウッソ~」と叫んでしまったけれど、それも助け合うやさしさからだと思うとつい笑ってしまい、心はホンワカしたものだ。
もっともそんな中で毎日学校生活を送らなければならなかった子どもたちにとってはホンワカばかりではなかったかもしれないが......。「分かち合い」に助けられたことはまちがいない。
【朝日小学生新聞「朝日おかあさん新聞」掲載】