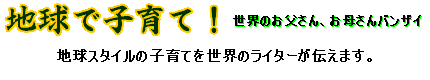世界の子育て事情
「見て見て! 赤ちゃんミミズを見つけたよ! お母さん、早く何か入れ物持ってきて!」
庭から息せき切って娘が家に走りこんでくる。小さなミミズ一匹に、まるで宝物を見つけたかのような興奮ぶりだ。彼女にとって別にミミズは珍しい存在ではない。そのへんの土を掘ればどこにでもいる。それでもミミズなどの虫の発見は、いつも彼女を有頂天にする。
そおっと触らなければつぶしてしまいそうな細さ、それでいて手の中で猛然と暴れる、強い生命力。キーウィ(ニュージーランド人のこと)・キッズは、庭のこんな小さな生物から、自分たち人間も属する自然の営みを学ぶ。
この国の多くの人々は一戸建てに住んでいる。自分の家のドアを開け一歩出れば、そこには庭が広がる。物理的には塀に囲まれている庭。しかし、考えようによっては、ニュージーランドの庭には"塀"などないことが、暮らすうちにわかってくる。
娘が友達の誕生日会によばれた時のこと。会のおしまいには、お返しとしてお菓子や小さなおもちゃが、招待された子どもたちに配られるが、その子のお返しは小さなかわいらしい花の鉢植えだった。それも大きな鉢にたくさん植わっている中から個々が好きなのを、小さな鉢に植え替え、持って帰るという趣向だった。
子どもたちは大喜び。どの子も「『マイ・ガーデン』に植えるんだ」と張り切って帰っていった。子ども用のガーデニンググッズや園芸本もあるほど、ニュージーランドにはガーデニング好きの子どもが多い。子どもたちはたいてい庭の一角に、自分専用のスペースを持っている。
そしてそこでお気に入りの花や野菜を育てる。種を植え、水をやり、肥料を与え、雑草を抜く。やがてそれは芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ。途中失敗して、枯らしてしまうこともあるだろう。植物はボタンひとつ押せば、一瞬のうちに花や実をつけるというものではない。
辛抱強く育てた野菜が実を結び、それを収穫、料理し、食卓を飾った時の誇らしい気持ち、また忘れずに水をやったおかげで、見事に咲いた花をお母さんにプレゼントする時のはずむ心。庭は子どもたちに喜びだけでなく、自信もプレゼントしてくれる。
しかし庭では常にプラスのエネルギーだけがあふれているわけではない。金魚など、自分が大切にしていたペットが死んでしまった時にも庭は重要な役割を果たす。泣きながら、「マイ・ガーデン」に穴を掘る。そしてそこに死んでしまった友達をそっと横たえる。お墓を作り、名前を書いてやる。そして大人に「金魚はどこへ行ったの?」と尋ねる。日々は過ぎても、時折そこに戻ってきて、小さな友達に、生きていた時と同じように声をかける。
もちろんペットだけではない。いつもはブーンと景気のいい羽音をたてて飛んでいるバンブルビー(マルハナバチ)が息絶え絶えで芝生に落ちているのを見るのも、昨日までひんやりとした影を作ってくれていたお気に入りの大木が風で倒れてしまったのを見るのも、ここ、庭なのだ。
遠くに行かずとも、家から一歩出ただけの庭で、自然界の一員としての掟を学ぶ。ここで育まれた知恵、良識、慈しみの心を持って、子どもたちは庭から一歩踏み出し、そしてどんどん歩き続ける。この国の庭には"塀"などない。ニュージーランドの庭は未来につながっている。
フィンランドでは、妊婦の検診は病院にではなく、テルヴェウスケスクス(保健センター)のネウヴォラ(相談所)に通う。家から車で5分とかからない保健センターでの私の担当の保健婦さんは、自身もアブダビに住んでいたことがあるという、やや年配の女性だった。「英語で話しましょうか、えええ、それともフィンランド語?」とゆったり話す様子が、話すというより昔話を読んでいるような感じ。「英語でお願いします」と答えながら吹き出しそうなのを堪えていた。
その後の検診は、出産までに月に1回、9か月に入って月に2回、臨月は毎週、と合計13回に渡って、尿検査、体重と血圧の測定、腹囲や子宮底の計測や、血液検査、血中ヘモグロビン量の計測が行われた。保健センターの医師による診察は、12週目、28週目と36週目にあり、超音波検査は、保健センターには設備がないため、北へ20キロほどのところにあるヒュビンカーの総合病院に自ら予約を取って出向けとのことだった。
余談だが、フィンランドでは、胎児の性別を教えたがらない医師が多い。さらに親としても、生まれてくるまで知らずに楽しみに取っておきたい、というフィンランド人が多い。知り合いのフィンランド人に、逆に何故知りたいのかと聞かれ、私が「名前を決めたり、育児用品を買い揃えたりするのに、性別が分からないと不都合」だと答えると、「へえー」と驚き半分、納得半分の顔をされた。
そんなわけで、ヒュビンカー総合病院での超音波検査では、先生をあてにすることなく自ら目を凝らして見ていたが、凝らすまでもなく、モニターに立派なモノが大写しに映っていた。担当の中年の医師は、英語は勘弁してという人だったので、夫にそのモノが何であるかを聞いてもらうと、もっと接写して「ああ、タマですね」と、いともあっさり認められた。
生まれてくる子が男の子であることがわかったところで、再び健康センターでの検診。例によって普通に話しているのに何もかもが「むかぁ~し、むかし」みたいな語調の保健婦に「男の子?それとも女の子?」と聞かれ「男の子です」と教えてあげると、腹囲を測った手を止め、「まぁ、それは楽しみね」だの、「息子さんは喜んだ?」だのと話を続ける。そして、あらゆる測定が終わったところで、椅子に座ると「あれ?」と首をかしげ、私の目をのぞきこむ。「あのぅ、私ぁ、何センチって言いましたかね?」――志村けんのけんバァさんか。数値の再確認をされたのは、これが初めてではなかった。
翌月の診察の日。駐車場からセンターの建物まで歩く途中、夫が言った。「きっと、今日も性別をきいてくると思うよ」私は、まさかぁ、と笑う。「賭けてもいい。5ユーロだ」と夫は引き下がらない。予言は的中し、保健婦は再び私の腹囲を測りながら胎児の性別を聞いた。夫は指をこすって"金払え"のジェスチャーをした。その後、「あとは産むばかり」という話になり「もう一人産んでるんだから、同じことよ」と微笑む保健婦に、夫が「ちょっと待った」をかけた。
3歳になる息子の通う保育園は、目黒・世田谷・渋谷どこからも近く、車での送り迎えも許可されていて便利だが、平凡な東京都内の認可保育園。園児の生活も日本の文化や生活習慣をベースにしている。お正月のお餅つきや豆まき、ひな祭りなどの行事があり、おやつにおにぎりが出る。
子供も親も先生も日本語でコミュニケーションし、日本ならではの保育園ライフを送っているのだが、ここには、両親のどちらかが外国人という園児が何人もいる。また、海外から転勤で日本に来ている駐在家族など、一時滞在の外国人家族の子供たちも結構いる。
日本に定住している人々で、家族のうち誰かが日本人ではないことはもう珍しくない。厚生労働省の調査でも、息子と同じ2006年生まれの日本の新生児で、親のいずれかが外国人の割合は30人に1人という。日本の多様化は進んでいるのだ。それでも「ハーフ」「ミックス」「帰国子女」「在日外国人」など、様々な枠はいまだに存在する。日本人の両親を持ち、日本で生まれ育ち、日本語で教育を受け、日本だけで暮らす、それらすべてを満たさない場合、「何かが違う」と周囲に受け取られたりする風潮は、まだある。
しかし、今こうして息子の保育園を見ると、日本がようやく多様化を受け入れはじめたのを感じる。私の子供時代よりはマシということか。当時、両親のいずれかまたは両方が日本人でない、日本で育っていない、日本語で教育を受けていない、将来日本で暮らすかどうかわからない、そういうわが子を「日本の普通の保育園」に入れても大丈夫かな、と昔の親たちは慎重にならざるをえなかった。私自身も多様性に不寛容な日本を何度も目撃し、経験した。
昔との違いを最も感じるのは、仕事の都合で一時滞在するだけの外国人家族がわざわざ日本の保育園を選ぶこと。こうした家族は、数年でまた日本を離れてしまうし、インターナショナルスクールや母国の教育システムを持つ都内の保育園・幼稚園もあるのに、日本の保育園を選択しているわけだ。逆に考えれば、日本人の海外転勤族が、子供を現地校に通わせるのと同じかな。居住地のライフスタイルを経験するのだ。
小さな息子にとって、保育園という日常の中でお友達を通して多様性に触れることができるのはいいことだと思う。まだわからないかもしれないけれど、広い世の中にあるもっといろいろな民族や言語、それぞれ違うライフスタイルがあることを知るきっかけを感じてほしい。人間の多様性の素晴らしさについて、全部違っているけど全部いいんだよ、って少しずつ話していきたいと思う。
息子は、3歳から6歳前まで、デンマーク発祥の森の幼稚園に通った。そこにはおもちゃも園舎もなく、晴れの日も雨の日も風の日も雪の日も、毎日朝8時半から4時半まで森で過ごした。四季を通じて日々変化する森の木々や草花、きのこ、虫たちや小動物、そして落ちている木の枝や石ころ、水たまりが遊び相手。それまで息子は、冬場は風邪をひくことが多かったが、森の幼稚園に行き始めて、目に見えて強く、たくましくなり、病欠もほとんどなかった。
そんな彼も、昨年8月から0年生として学校に通い始めた。放課後は夕方まで、学童クラブで過ごしているせいか、息子は突然「室内遊び」に目覚めた。これまでほとんど興味を示さなかったレゴを手始めに、Yu-Gi-Oh!などのカードゲームに熱中、ついにはプレステ、Wiiの虜となった。毎日の食卓での話題と言えばレゴ・スターウォーズのゲームで今日はどのステージまで行けた、というようなことばかりで、このまま「バーチャルワールド」の住人になってしまうのか、と少し不安になった。
先日、息子と愛犬ポルカを連れて自宅近くの小川沿いを散歩していたときのこと。突然、ポルカが興奮した様子で小川に飛び込んだ。そこにはカモがいて必死に逃れようとしたのも束の間、元々猟犬であるポルカは、あっという間にカモを口にくわえて土手に戻ってきた。ほとんど瀕死の状態だった。シカや野うさぎ、キジを夫とともに家に持って帰って食べた経験のある私だが、これにはさすがにショックを受け、カモを前に立ちすくんでいた。すると、すかさず息子が「まだ完全に死んでいないみたいだから、石で頭を叩いて楽にしてあげたほうがいいよね?」と言った。もう助からないのだから、早く死なせてあげた方がよい、ということを、息子は知っていたし、冷静だった。
ちょうど夫が様子を見に来た。カモを家に持って帰って食べようということになった。私はふと、息子に「びっくりしなかったの?」と聞いた。彼は「少しびっくりしたけど、家で大事に食べてあげれば、きっとカモさんもそれほど悲しまないよ」と言った。そして、「ママ、忘れたの?僕にはバイキングの血が半分流れているんだよ」とウインクして犬と一緒にわが家へ走って行った。
東京や横浜といった都会暮らしから、デンマークの田舎町へ移り住んで、もうすぐ7年が経とうとしている。より自然に寄り添った暮らしに慣れてきたつもりでも、まだまだハッとさせられるような出来事に多く遭遇する。
ゲームに夢中になってばかりいると思っていた6歳の息子のとっさの行動に、自然との関わり方がしっかり身に付いてきていると感じられ、少し頼もしく思った。
≪ニールセン北村朋子/プロフィール≫
デンマーク・ロラン島在住のライター、ジャーナリスト、コーディネーター。再生可能エネルギーの利用等の環境や食など、地球と人にうれしいライフスタイル追求がライフワーク。小学0年生(6歳)の男児の母。森の幼稚園の運営委員の経験を活かし、子供が家族や社会、自然と関わりながら、子供らしく生きられる環境について考える日々。ロラン市地域活性化委員、デンマーク・インターナショナル・プレスセンター・メディア代表メンバー。
現在、世界でも一、二を争う程、少子化が進んでいる韓国。2005年に女性が生涯に産む子どもの数を表す出生率が1.08にまで落ち込み、その後、2007年には1.26に回復をしたものの、依然として少子化に歯止めがかかっているという状況ではない。
韓国でも、都市部では核家族化が進み、一家庭に於ける子どもの人数は1人、即ち一人っ子の家庭が目立つ。韓国で何故、日本以上の少子化が猛スピードで進んでいるのかを考えてみたい。
日本でも韓国の教育事情については度々、マスコミでも取り上げられ、詳しくは知らなくとも、「韓国=教育熱心」という印象を持っている人も多いのではないだろうか?特に、最近では幼児期からの早期教育を重要視する傾向が高まっている。例えば、英語教育や、韓国の国語に当たるハングルの読み書きや計算の小学校入学前までの習得。また、各幼稚園や保育園でも保護者にいかに園のプログラムが優れているかをアピールすることに試行錯誤している。
また、小学校就学前の幼児を対象とした英語塾や学習塾の生徒の獲得合戦も過熱気味である。このようなことから、韓国で子ども一人当たりにかける一月の教育費は中産層の家庭で100万ウォン(日本円で10万円)に相当するという試算も出ている。これでは、子どもを一人当たり成人まで育て上げるのも、親の負担は非常に大きなものとなり、子どもを一人以上産むことを考えざるを得ないというのが親の本音なのだ。
儒教の影響が現在でも残る韓国では、「学を究めることこそ、将来が約束される」という考えが「学歴至上主義」につながっていると言える。日本でも教育への関心は高いという点では同じだが、韓国では部活動が盛んに行われる環境がなく、日本のように勉学以外のスポーツや技術などの分野でも打ち込める環境が少なからずあるというのが韓国との差である。単に大学に進学するためだけの勉強ではなく、様々な人に門戸を開き、学べる環境を整えていかないことには、韓国の少子化と教育の質の低下は避けられないのではないだろうか。
子どもの成長過程でさまざまなお祝い事や行事があるのはネパールも同じだが、カトマンズ盆地土着のネワール族の女性は一生に3度結婚するといわれ、大変珍しい結婚の儀式を行う。
旧市街のレンガ造りの建物に囲まれた広場に、赤い衣装にきらびやかな金の装飾品を身につけ、お化粧をした5歳から10歳頃の女の子たちが集合していた。この日は初めての結婚「イー」の日。お相手は不死身とされる果実マルメロの実の一種で、将来未亡人になることがないようにという意味があるそうだ。朝から司祭によって祈祷が執り行われ、女の子たちは縁起物のほら貝、牛乳、お香、米、染めた綿糸などの前に座り、一連の儀式は3日間にわたることもある。
いよいよ3度目が本当の人生の伴侶との結婚だ。果実や太陽は神の象徴で、嫁ぐ娘の健やかな成長と幸せの願いが込められた人生儀礼の伝統が今も変わることなく受け継がれている。
フランスでは、親が子どもにあくまで真実を語ろうとする、その真摯な、でもちょっと「?」な姿勢に驚かされることがある。
たとえば、親が子どもに離婚の理由から経過まで詳細にわたって打ち明けるので、まだ舌足らずな子どもの口から「家庭裁判所」やら「調停」、「弁護士」などという単語が飛び出し、啞然としたことがある。
養子縁組みをするカップルも多いが、まだ、ほんの乳飲み子に「あんたのね、本当のお母さんは南米のコロンビアっていうところに住んでいるんだよ。でもね、お母さんは貧しくてあんたを育てられない、だから、私たちが代わりに引き取ったんだよ、おーよしよし」などと、四六時中、執拗に説明している。
この「言葉のもつ魔術」は、とくに母子の間で深く信仰されているようだ。「子どもは知らなくてもいいことって、あるんじゃない?」なんて言おうものなら、すかさずバッシングされる。「重大でショッキングなことこそ、隠さないで、子どもがわかろうとわからまいと言わなくてはいけないのよ。口に出していうことで、私も、問題を客体化できる。そして、子どもも『そんなに大したことじゃないのかもしれないな』って思えるようになるの」と。
小児心理の権威として、フランスのママンたちの絶対的支持を得て読み継がれているドルトー氏の著書によれば、夜泣きをする、食欲不振などの症状をもつ赤ちゃんの多くが、この「話せばわかる」術で快方にむかうそうだ。
【朝日小学生新聞「朝日おかあさん新聞」掲載】