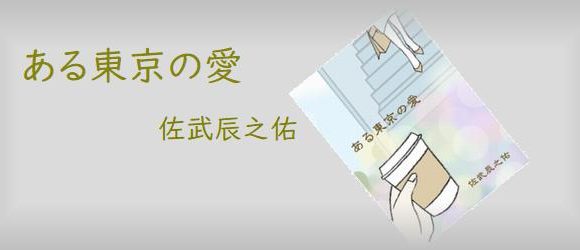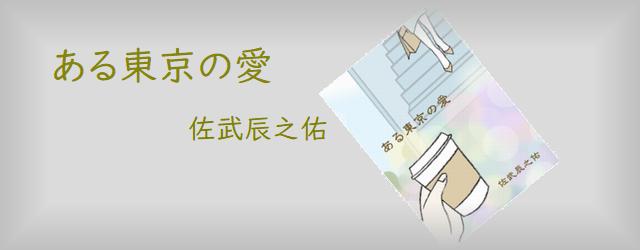
そして僕はコーヒーショップのカウンターで彼女の身体を思い出す。写実主義の画家が描いた精密な油絵のように皴のひとつひとつ、体毛の一本一本まで見落とさないように。彼女の身体だけではなく僕と彼女の匂いが染み込んだ布団や、僕の部屋の照明、セックスのあとの気だるさ、その季節の湿度にいたるまで細かく僕は思い出す。
彼女の体のラインを思い出し、脇の下の影や、わき腹のたるみ、白くやわらかいふくらはぎ、不器用な足の指、そして彼女の陰毛。僕の指先に触れた彼女の性器の温度を思い出し、鼻のなかに残るその匂いを思い出し、吸い込まれていく僕の性器を思い出す。
連続写真を一枚一枚丹念に眺めるように僕は彼女の表情を、僅かな感情のブレを思い出す。ある写真では大きく目を見開きながら顎をしゃくり上げ、別の写真ではしっかりと目を瞑って下唇を噛んでいる。彼女の表情は激しく僕を求めている。
そうしていつの間にか僕は幻の彼女を抱いている。夢のなかで、夢の僕が、夢の彼女を抱いている。それは現実に彼女を抱いているよりも生々しく思えてくる。彼女の力強い生命力が僕を迎え入れ、彼女の口からこぼれる吐息を、その生命の匂いを、感触を僕は思い出す。彼女は僕の口の中で舌を動かし、何かを捜し求めるかのように生温かい粘膜を摩り付けてくる。彼女が上に乗り、彼女の髪が揺れ、互いの手を取り合って単純なうねりに身を任せる。僕は彼女のすべすべしたおしりに手を回して揉み解す。僕の指の腹で彼女の肛門を撫でる。彼女は腰を仰け反らせ、呼吸と共に裏返った声を出す。僕の性器と彼女の性器が擦れあうたびに彼女の表情はメトロノームのように規則正しく揺れ動いている。彼女のねばねばの体液はだんだんと僕の時間を溶かして行く。僕の記憶はどこかでばらばらに弾けてしまう。夢と現実が分水域を超えて、何かが壁にぶち当たる。
僕はそのなかで彼女と何か大切なものを共有する。言葉にならないものを。形にできないものを。どのくらい大切なものなのかを彼女に伝えることはできない。でも彼女はそれを知っている。それは元々彼女のものであり、僕のものだからだ。
それにしても彼女は一体何を求めて僕なんかとこういう関係になっているのだろうと思う。僕が彼女を求めるのはすごくはっきりしている。男として美しい女性がいたら抱きたいと思うのは自然なことだ。当たり前のことだ。なんならこの街に大声で叫んでもいい。僕は男なんだと。美しい女性を抱きたいんだと。周りの人々はびっくりするかもしれない。でも当たり前のことなのにわざわざ口に出して言う人は少ない。僕は男だ。それでいいじゃないかと思う。
でもわからないのは彼女のほうだ。彼女ならもっとかっこよくて、頭が良くて、気の利く男がいくらでも言い寄ってくるだろう。こんな定職もなくて、金もなくて、頭も禿げかけてきている僕の何がいいのだろう?これもまた考えてみてもしょうがない。
誰かが店内で大きなくしゃみをした音で僕は我に帰る。ウォークマンのボリュームを下げて周りを見渡してみる。店内の人々はほとんどが入れ替わっているけど、白いジャケットを着た女の子はまだ暇そうにして席に座ったままだ。本当にいくところがないのかもしれない。もしかしたら僕が声をかけるのを待っているのかもしれない。
ふと思い出してバッグからケータイを取り出す。マナーモードを解除するのを忘れていたので気がつかなかったけどメールが来ている。メールは友人からだ。
「今夜なにしてんの?」とある。
画面を良く見ると今日は土曜日であることがわかる。それじゃあ彼女から連絡がこないのは当たり前だ。土曜と日曜は彼女と会うことはない。僕は今日が何曜日かなんていちいち気にしてない。
僕は友人にメールを返す。
「特になにもしてないよ」と。
すぐに返信が来る。
「飲みにいこうぜ」
「いいよ。いつもの駅の北口、改札7時」と僕はメールを打つ。「オーケー」と返信がくる。オーケーの文字の後には笑い顔をした顔文字が描かれている。こうやって世の中はどんどんと複雑になっていく。
7時までにはしばらく時間があるので僕はCDショップにいくことにする。2時間ぐらいは音楽を聴きながらぼーっとしていたことになる。2時間分ゴミが生まれて、不法投棄された。
僕がトレイを返却口に返すために席を立つと白いジャケットの女の子も立ち上がる。店を出る前に僕はトイレに入って用を足す。トイレから出てくると階段付近の席に白いジャケットを着た女の子が座っている。ウォークマンはしていない。僕は女の子の横を通り過ぎて階段を下りる。
土曜日だという認識をもって街を眺めてみると確かにそこには大勢の人がいる。ガラス張りのCDショップのなかでは人が多くて視聴コーナーはいっぱいになっているし、レジには長い列を作っている。人々は心地よい場所を求めてふわふわと彷徨っている。僕もクラシックコーナーから始めて、ジャズ、ブルース、ロック、クラブ系に至るまで順々に回ってゆく。そしてこれだけCDの数がありながらまともなものを選ぶのに一苦労することに足踏みする。こんなひどいものが飛ぶように売れていることについて、この国の将来について、僕は真剣に心配してしまう。これだけCDがたくさんあるのなら僕の作ったものも見えないように、どこかの影にでもそっと忍ばせてもらえないだろうかと思う。どこかの物好きな人がもしかしたら買ってくれるかもしれない、と。でも世の中はそんなに甘くない。僕の付け入る隙がないぐらいぎしぎしと居場所を誇示しているからだ。
僕はCDを買うにはとても慎重になる。お金を使うということは僕の自由時間がそれだけ縮まるということになるからだ。お金がなくなると僕はまた彼らの渦のなかへ、身を削られるデジタルな流れのなかに戻らなくてはいけない。できることならそれは先へ伸ばしたいというのが本音だ。
でもいくら慎重になったところで失敗することはかなりの頻度になる。視聴できればその確立は減ることになるけど、やっぱり店のなかで落ち着かずに聞くのと、部屋に戻って落ち着いて聞くのとでは受け止め方が全然違う。これは良さそうだなとジャケットを見て買って、ぴたりとはまったときほど嬉しいことはない。自分では何もしていないくせに、大勝利を収めたような満足感を得られる。ついつい友達にも教えてあげたくなる。
しかしそういうことはほんとにごくまれなことだ。一年に一度か二度ぐらいしかない。だいたいはCDを再生して10秒もしないうちに結果がわかる。安っぽい音の割れ方と、ざらざらした深みのない音が耳に入ってくると同時に「はずれ」と言って彼が僕の頭を叩く。やってしまったな、と僕は思う。レジに持っていって返品してしまいたくなる。すいません、買うの間違えちゃって、と。でももちろんそんなことはしない。そんなことを繰りかえしていたら店にも迷惑がかかるし、僕も下らない音楽を作るひとりとして、誰かが必死で作ったものにはそれなりに敬意を払う。それでも反省はする。すごく反省する。冷たい滝に打たれて精神統一したくなるぐらい反省する。下らないことに金を使ってしまったことに、迷ったほうのもう一枚のほうを買うべきだったということに。しかし結局はそういうことも時が経てばしだいに受け入れていくことになる。どこか遠くで起こった静かな死を遠くから見守るようにして、時のなかに、記憶のどこかに消えていく。
今日はお気に入りのアーティストの新作が出ている。僕は無難な選択をし、それをレジに持っていく。それから7時に向けて目的の駅まで電車で移動する。車内で買ったばかりのCDを聞く。やっぱり大御所のアーティストというのは音には迷いがなく、それでいて余裕があり、バランスも整っている。偉そうなことばかり言っている僕とは全然違う。でもどこがどう違うのかと聞かれてもよくわからない。才能なのだろうか? 才能とはそもそも何を指し示すのだろう?ある穴があるとして、その周りをどれだけ綺麗に埋められるかということなのか、どれだけ場所を提供できるか、ということなのか?そんなことを考えていると電車は目的地に着く。
僕は電車を降りると空を見上げる。空は暗くなっているけど、ネオンにかき消されて星なんか見えない。それに後ろから押し寄せてくる人々の邪魔になる。
改札に行ってみてもまだ友人の姿はない。僕は壁に寄りかかって前を通り過ぎてゆく人々を眺める。どこから湧いてくるのかその波は止むことはない。ドブの匂いが充満した砂漠の波のなかから聞こえてくる止まない鼓動のように思えてくる。そしてこれは果たして現実に起こっていることなのだろうかとさえ思う。これだけ多くの人々がいながら、祭りのような大賑わいがありながら、誰もがここで生きていないのだ。そんなものを見ていても眼が疲れてくるだけだ。
改札を出てすぐのスクランブル交差点はびっしりとパズルのように人々で埋め尽くされている。信号が青になるとパズルは一瞬だけ形を失いそれぞれの方向に進んでいくけど、信号が点滅し始めると人々は足を速め、クラクションが鳴る。そしてまた元通りのパズルに戻る。
街頭の大きなスクリーンではチカチカと映像が入れ替わり、大きな音でCMの音が流れている。ウォークマンをしてもその音はかき消すことができない。僕は自分が井戸のなかにいるカエルなんだと思う。たとえ空の高さを知っていたところで、僕はここから逃れることはできない。
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。