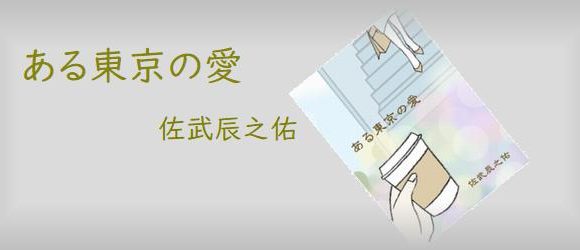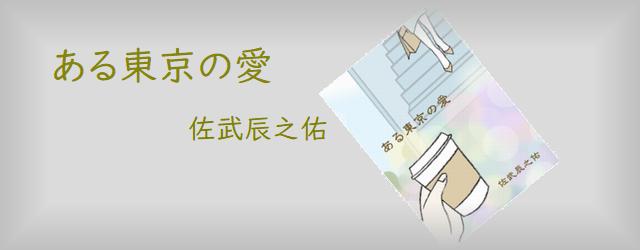
彼女のことを考えると同時に、彼女の夫のことを考える。彼女と彼女の夫のことを考えるのは、いつの間にか僕のなかでセットになっている。彼女の夫には会ったことはないけど夫の書斎のことは知っている。高い家賃のマンションの中にある夫の書斎。そこには高価なステレオセットがあり、クラシックのCDがずらりと並び、どっしりとしたマホガニーの机の上にはマッキントッシュのコンピューターが置いてある。本棚には経済学や経営学の難しい専門書が並び、重苦しく濃密な時間が漂う。彼女の家のリビングにしたって同じようなものだ。ヨーロッパ製の幾何学的なデザインのソファがあり、シルクの絨毯があり、落としたら簡単に割れそうな食器が棚にきちんと配列された効率の良いピカピカのシステムキッチン。
ぴっちりと密閉された寝室で僕は彼女を抱く。そのベッドにしたってそこいらのホテルにあるちゃちなものじゃない。ハンドメイドの固すぎもせず、やわらかすぎもしない、寝転んだだけですぐに眠ってしまいそうな極上のものだ。
僕は彼女のマンションに行くたびに、僕の住んでいるアパートとは遠くかけ離れた場所だと思う。彼女の夫はこんなところに住みながら、それを十分に味わっているのだろうか。ときどき僕は自分が彼女の夫になったような錯覚を感じる。それはあくまでも錯覚だ。でも彼女を抱いているときはここが僕のあるべき場所であるような気がしてくる。僕の記憶はどこかで入り混じって彼女の顔に映し出される。
僕はケータイを見る。そこに着信履歴はない。時計は午後の3時を示している。彼女から連絡があるとすればいつもきまって昼過ぎなので今日はもうだめだろうと思う。部屋にいてもすることはない。僕は外に出ることを考える。
いつもと同じ街。同じ日常。デパート前の広場では、だぼだぼの服を着た若者が座り込み、その隣には制服を着た女子高生がいる。コンビニでは立ち読みをしている人々が肩を擦り合わせるようにして居場所を守っているし、角のパチンコ屋の自動ドアが開くとがやがやとした騒音が漏れてくる。人々は勝手気ままに歩いていて、どこに向かっているのかも自分ではわかっていない。みんな夢遊病者のように片手にケータイを握り締めている。自分の居場所を誰かに知ってもらわないと不安でしょうがないのだ。
そんなことを考えると僕は外に出る気がなくなる。どこへ行ってもどうしようもないような気がしてくる。そうすると“彼”が現れる。でも僕は“彼”が現れてガミガミ言われるのを思うと外に出たほうがましなような気がしてくる。
僕は顔を洗い、歯を磨き、服を着替えて外に出ることにする。ようやく僕にとっての一日が始まる。僕はヘッドフォンをつけてしっかりと耳を塞ぎ、アパートのドアを開けて外に出る。でもいくら耳を塞いだところでそこにある匂いは、街の沈殿した匂いは鼻から入ってくる。
駅までの道のりを歩きながらどこに行こうかと考える。商店街を通り抜け、小さな信号の交差点を渡りながら考える。店に掲げられた幾つもの看板や数字の列を通り過ぎる。周りの人々は僕が何を考え、どこに向かっているのか知る由もない。僕はあくまでも平静を装い、彼らのなかを通り過ぎる。街の人々は口裏を合わせたように頑なに沈黙を運び続けている。ヘッドフォンをつけていても、彼らの視線が、歩き方が、息遣いが僕にそう告げる。僕に向かっては何ひとつ語りかけてこない。
どこにも行くところがない。行きたいところがない。改めて僕はそう思う。駅に向かう足どりは変わらないけれどもそこに行ったところで、僕の行きたいところはわからない。
駅にはさまざまな可能性がある。さまざまな可能性の出発点だということができる。その気になれば、そこを足がかりにして今まで行ったことのないようなところにも行くことができる。海外にだって行くこともできる。でも実際問題として、今のところ海外になんて行きたくない。可能性は壁に遮られる。
いっそのことどこか海に行ってみようかと思う。穏やかな水平線を見て、世界の広さを感じることができれば少しはましな気分になるかもしれないと。ゆらゆらと揺れる波を見ていれば時間を忘れて何かいいことが起こるかもしれないと。でもそれも思ってみるだけで僕は海になんて行かない。この街の周りにはまともな、心を開けるような海なんてないことを知っているからだ。それに今から海に行ったとしてもついた頃には暗くなっているはずだ。一日は日が暮れるのが早い。どこにも行けないまま気がついたらネオンが灯り始めている。
そして遠くに行くには金がかかる。金がなくなるということは、働いてない僕にとって、収入がない僕にとっては僕の猶予を、他愛のないものかもしれないけど僕の限られた自由な時間を自分ですり減らすということになる。
僕は3駅離れた街までの切符を買い、電車に乗る。そこまで行ったところで何があるわけじゃない。チェーン店のコーヒーショップとチェーン店のカレー屋とチェーン店の定食屋、バーガーショップ、本屋、レコード店、どこにでもあるような街があるだけだ。じゃあなぜそんなところに行くのだろうか?
「無駄なんだよ、無駄。おまえはなんにもわかってないな」“彼”が聞こえないように僕に耳打ちをする。
上り電車は出たばかりみたいでプラットホームにはまばらにしか人がいない。でも次の電車が来る頃にはまるで決められたことのようにそれなりの数の人々が集まってくる。僕はこの街の一員として、夢の住人として、プラットホームに立って電車を待っている。僕はケータイをマナーモードにし、曲を入れ替えて電車に乗る準備をする。ボリュームを小さくし、彼らに僕の存在を知られないように気を配る。ドアが開くフロントポジションに移動し、白線を越えないようにして、そしてそんなそぶりを周囲に悟られないようにして僕は電車を待つ。
電車がプラットホームに入ってくるとどうしても車内に目がいく。どれぐらい人が乗っていて、どのくらいそれが僕にのしかかってくるのか、それを計算する。
思ったより電車は空いている。いくつかの席が空いているのが見える。僕はドアのそばの手すりをしっかりと握り、席には座らない。そんなところに座ってもろくなことがない。こんなことがなかったらこの街はもっとましなところだろうと思う。シートには彼らのよだれがべっとりと張り付いているからだ。彼らの匂いだけではなく、価値観や、人生観や、道徳がそこでは待ち構えている。そんなところにケツを下ろすくらいなら立っていたほうがよっぽどましだと思う。
僕は音楽を聴きながら電車に揺られている。窓越しに移る景色はとらえどころがなく、壁の中を進んでいっているように思える。電車のなかに吊り下げられている広告に目がいく。そんなものは僕にとってどうでもいいことだと思いながらも、他に見るものがないので知らず知らずのうちにそこにある文字が目に入る。
目的の駅で電車を降りると歩いてコーヒーショップに向かう。レジでコーヒーを頼み、トレイにコーヒーと灰皿を載せて二階の席に行く。ほとんどの席は埋まっている。誰もが自分の座れる、自分のおしりを落ち着ける場所を求めてこんなところにやってくる。窓際のカウンターの席が空いている。僕はそこに座り、ガラス張りの向こうの街を眺める。周りに聞こえないように鼻から長いため息をつく。
右側の髪の短い女性は参考書のようなものを開いて勉強している。左側のスーツを着た20代後半ぐらいの男はノートパソコンを開いて忙しそうにパタパタとキーボードを叩いている。
ガラス越しの街からはすぐ真下に交差点が見える。
信号が青に変わる。
人々は向こうからこちらに、こちらから向こう側に移動を始める。
信号は青だ。
横断歩道の手前でケータイを耳に当てている男が、慌てて交差点を渡ろうとした男とぶつかる様子が見える。ぶつかったほうの茶色に長い髪を染めた男は振り向いて何かを言う。ケータイの男とぶつかった男は言い合いになったみたいで、ついには取っ組み合いになる。
信号は青だ。
二人は横断歩道の真ん中でお互いに掴みかかる。胸元を引っ張り、ぶつかった男が殴りかかる。ほとんどの人々はそれを横目で見ながらもこちらから向こうに、向こうからこちら側に渡り終える。信号は青から黄色に変わり、赤になる。
信号は赤だ。
男たちはまだ取っ組み合いをしている。両サイドの車から一斉にクラクションが鳴り、その音はガラス越しのヘッドフォンをした僕の耳にも響いてくる。
確かに何も変わらない。改めて僕はそう思う。たしかに、なにも、かわらない、と。
とたんに“彼”が耳元で囁く。
「なあ、もうわかったか?」と“彼”は言う。「おまえにはどこにも行くところがないじゃないか。彼女がいなかったら、おまえはどうすることもできない。どこに行きたいかも自分でわからない。そうだろ? いつものようにおまえは自分の特等席に戻ってくるだけだ。この下らない街の、下らない日常のど真ん中にな」
僕は聞こえない振りをする。振りをしたところでほんとはしっかりと聞こえている。カップを口に運び、また曲を選んで入れ替える。
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。