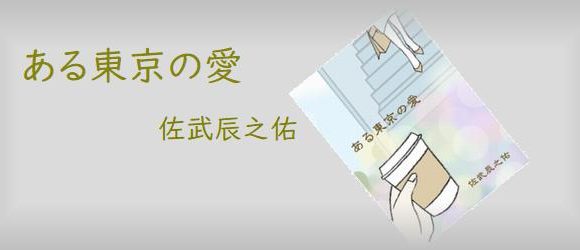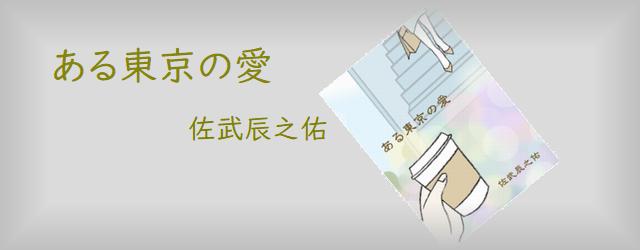
このコーヒーショップにやってきたのは僕がここで彼女と会ったからかもしれない。そんなロマンチックな気分はどうでもいいと思うんだけどなぜだかまたここに戻ってくる。偶然にも今、僕が座っている席にそのときも座っていた。そして同じようにウォークマンを耳にあてて音楽を聴いていた。彼女は僕の右側の席に座った。あれは一昨年の冬のことだった。
彼女は僕の隣にやってくるとコートを脱ぎ、椅子の背もたれにかけ、小さなプラスチックの袋を足元に置いた。手袋を取り、トレイに乗せた飲み物をテーブルの上に置いた。僕は目の前の人の流れをぼんやりと見ていた。
彼女は席に座ると足元のプラスチックの袋を開けて一枚のCDを取り出した。僕は自然にそこに目がいった。CDはモーツァルトのレクイエムだった。でも彼女はあまり興味もなさそうにすぐに袋にしまった。今時そんなものを聴いているのはどんな人だろうと思ったけど僕は隣を見ないようにした。この街では人の顔を見るのにもいちいち理由を探さなくてはいけない。
でも僕は隣から見られているような気がした。彼女が僕を見ているような気がした。僕は横目で彼女を見てみた。彼女は間違いなく僕を見ていた。でも僕は彼女を知らなかった。それでも彼女は僕を見ていた。僕は記憶を引っ張りだしてきてどこかで会ったことがあるのだろうかと考えてみた。大学時代の先輩、飲み会のメンバー、仕事の関係。でも僕が覚えているかぎり一致するものはなかった。それに彼女は少し驚いたような顔をして僕を見ていた。3秒間ぐらいは見つめ合ったかもしれない。3秒といえども知らない人同士が見つめあうのには十分に長い時間だ。
僕は正面を向き直ってもう一度記憶を細部まで思い出そうとした。もしかしたら小さい頃にあった親戚のおねえさんかもしれないと。そうじゃなくて一見まともそうに見えるだけで頭のおかしい女なのかもしれない。頭のおかしい人間はどこにでもいる。石を投げたら簡単に当たるだろうけどその後が大変だ。
彼女は僕の肩を叩いた。僕は眉をひそめ、ウォークマンを外しながらもう一度彼女を見た。でもやっぱり彼女には見覚えがなかった。でも彼女は頭のおかしい人には見えなかった。頬はすっきりとして目は大きく、髪は美容院に行ってきたばかりのように綺麗にウエーブがかかって肩の辺りまで伸びていた。美人だといえる部類だった。服装も白いカーデガンに細身の黒のスカートという格好でさっぱりとしていた。僕よりは3歳ぐらい年上に見えた。
「何を聴いてるの?」と彼女は言った。
僕は少し戸惑って「失礼ですけど、どこかで会ったことありますか?」と聞いた。
「さあ、ないんじゃない」と彼女は言った。僕はわけがわからなくなった。
それが僕と彼女の出会いだった。今思ってみても夢のような話だ。ある日突然誰か美しい人が僕の元にやってくる。見落としていたどこかの扉が勢いよく大きな音で開くみたいに。僕はもっと若い頃はそんなものを願っていたかもしれない。そんなことは起こるはずがないと思いながらも、どこかでそれが起こることを期待していたかもしれない。でもそんなことが起こるはずはないということはこの街で時間が過ぎてゆけばゆくほど現実のものになっていった。そしてかつてそんなことを考えていたことすらバカらしく思えてきた。それはくだらない妄想で、くだらない現実逃避だった。
でもそれは僕の身に起こったことだった。それを僕は選んだのだ。もしあのとき僕が彼女を無視してそのままだったら、アパートに戻ってからしばらく後悔したかもしれない。何日かその出来事を頭のなかで繰りかえして、しばらくすればそれを忘れていっただろうと思う。日々のなかで考えることはいくらでもある。それこそ無限にある。それが実際何の役にたつのか、そこから何か有益なものが生まれるのかといえば、もちろんそうじゃない。僕の頭のなかはゴミ箱と直結していて考えたものは生まれてまだ産声をあげる前にゴミ箱に放り込まれる。毎日ポストに入れられるチラシと同じだ。ろくに見向きもされずにそのままゴミ箱と仲良く暮らしてゆく。
僕は見ず知らずの人と唐突に話したりはしない。この街はそんな見えないルールがあるのだ。それは街中の人々の顔にも、壁にも堂々と書いてある。我、関せずと。どうかこちら側に来ないでくださいと。願うようにそれは書いてある。
それでもそのときは何の運命か知らないけど彼女と話をしてみようと思った。何かが僕に忍び寄ってきて、いつの間にかどこかへ連れ去ったのだ。
「え、何を聴いてるのって、音楽のこと?」と僕は彼女に言った。僕は何かを考える前に反射的にそう答えていた。
「そう、音楽のこと」と彼女は言った。
彼女は少し微笑んでいるように見えた。それは素敵な微笑だった。街角の大きな看板に描かれているような理想的な微笑。でもこのときでも僕は何かのいやがらせか勧誘かもしれないと思っていた。そういう話は友達からよく聞くし、それこそどこにでも転がっているからだ。
「レディオヘッドだけど」僕は答えた。
「ちょっと聴かせて」と彼女は言って僕は彼女にヘッドフォンを渡した。
後から聞いた話だけどこのとき彼女もそうとう緊張していたらしい。彼女はそれまでに他人に声をかけられることはいくらでもあったけど、彼女から声をかけたことはなかった。彼女はベッドのなかでそう言った。
「じゃあ、どうして声をかけたんだ?」
「あのときはどうしてもそうしたかったの。何かを感じたのよ。それでよくわからないまま声をかけちゃったの。あなたも相当困っていたみたいだったわね。私も何にも考えてなかったからどうしていいかわかんなくなっちゃって、それであなたが音楽を聴いていたから話のきっかけとして手っ取り早いことを言っただけ。なにがどうなるかなんて考えてもいなかったわ」
彼女は僕に腕を絡めてくる。彼女の胸が、柔らかい肌が僕のわき腹に当たる。シーツには僕と彼女の匂いがひとつになっている。生物の体液であり、時間がひとつになった匂いだ。僕の身体はもう一度彼女を求めようとする。彼女の中に入りたいと思う。そこには失った僕の世界があり、奪われた僕の記憶がある。ほんの束の間でも僕はそれをもう一度味わいたいと思う。
「なんか、ヘン、ね。この音楽。音楽じゃないみたい」ヘッドフォンを耳に当てた彼女はそう言った。すぐに僕にヘッドフォンを返した。
「だからいいんだよ」と僕は言った。「ミュージシャンは音楽を作ろうとする、画家は絵を描こうとする、作家は物語を書こうとする。だからダメなんだ。だからゴミみたいなものばかりが生まれるんだ」僕はそう言ったけど、なんでこんなことを言ってしまったのかと考えた。
「ふーん」彼女は不思議そうな顔をした。それもそうだと僕は思った。いきなり初対面の人に向かって言うようなことじゃない。
「難しいこと言うわね」
「君だってモーツァルト聴いてるんだろ?」
「ああ、これね。これは夫に頼まれて買ってきただけ。私は音楽ってそんなに聴かないの」
僕は早々に彼女が結婚していることを知った。当たり前のごとく僕のテンションは、僕のなかの何かは小さく萎んでいった。
でもこのときばかりではなく、それは今でも僕のなかで大きな問題として、目の前の壁として立ちはだかっている。たぶんそうだろうと思う。もしかしたらそれはさほど問題ではないのかもしれない。僕が考えているほどたいしたことはないのかもしれない。それがどこかにいっても、僕の問題は僕のなかにあるからだ。それがなくなるということはないし、何かがすり替わったところで、壁の一枚をぶち壊したところで何の役にもたたない。
「何か音楽の仕事でもしているの?」と彼女は聞いてきた。
僕は少し言葉に詰まった。こういうことを答えるのにはそれなりに言葉を整理しなくてはいけない。
「音楽の仕事をしているっていうわけじゃないんだ。それで飯を食ってるってわけじゃない。ライブをしたり、インターネットに作った曲を乗せたりはしているけど」
「じゃあ仕事は?」
「今はしてない。金がなくなってきたら適当に働いてる。金が貯まったら仕事を辞めて曲を作る。君は何をしているの?」僕は自分から質問をしてみた。
「私は主婦よ。働いてないの。あなたと同じね」
「これって、何かの勧誘かなんか?僕は特定の神は崇めないことにしてるんだけど」
僕がそう言うと彼女は笑った。回りの人が振り返ってこっちをみるぐらいよく通る声だった。彼女は口に手をあてながら彼女は笑い続けていた。何がそんなにおかしかったのかわからなかったけど彼女が笑ったことによって少し緊張がほぐれたようだった。
「あなたっておもしろいのね」
「そうかな?今時の神はユーモアに救いを求めるからね、ヘイ、ヨウ、ファックユー」
彼女はもう一度笑った。僕もつられて笑ってしまった。
「ねえ、音楽ってラップとかやってるの?」
そう言われるとまた考えてしまった。そういうことを一言で言うのは難しい。
「ラップはやってないよ。どんな音楽をやってるのかって聞かれても答えるのは難しい。うまく言えないんだ」
「楽器は何かできる?」
「大学の頃はバンドを組んでギターをやってた」
「私は小さい頃はピアノをやってたの。でも今じゃ全然だめ。たぶん向いてなかったの。親に言われるままにやってただけなの。ねえ、それ何飲んでるの?」彼女は僕の飲み物を指差した。
「アイスカフェラテだよ。アフリカの匂いがするやつ。君は何?」
「私はただのブレンドコーヒー。あなたって外国に詳しいの?」
「なんで?」
「だってアフリカの話をしたじゃない」
「ただの冗談だよ。あまりおもしろくなかったみたいだけど」
「どこか行ったことある?」
「どこかって海外に?」
彼女は頷いた。
「ないね。イギリスに行ってみたいとは思うんだけど。君は?」
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。