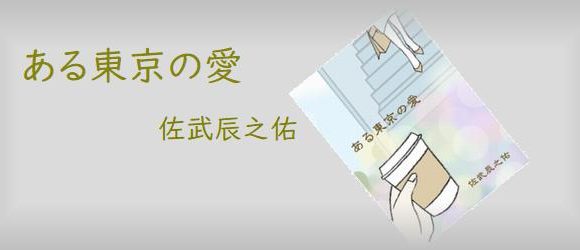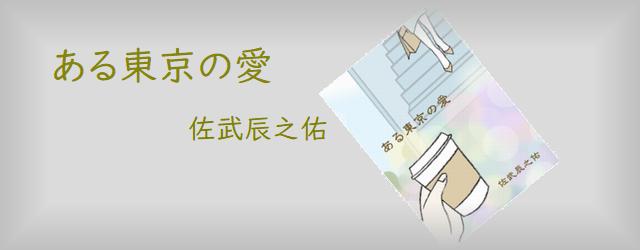
けっこう話が弾んできたのに僕は彼女の名前を聞かなかった。それにどう見ても年上の女性に「君」なんて呼び方をするのもどうかと思ったけど、僕のほうも余裕がなかったのだ。いや、そうじゃないかもしれない。僕は名前なんてものに興味がないのかもしれない。それはただの記号で、イメージを細分化させるだけだからだ。後々僕が彼女の名前を聞いたときもなんだかしっくりこなかった。もっとふんわりとして気品がある名前だと思っていたからだ。
「私はね、オーストラリアに2回でしょ、バリと、タイと、イタリア、ハンガリーと、ネパール。そんなものかしら」
「ずいぶん行ってるんだね」
「そうかしら。あなたはどうしてイギリスに行きたいの?」
「ビートルズとレッドツェッペリン、レディオヘッドが生まれたところだからさ。それだけでも行く価値はあると思うね」
「ビートルズ以外は知らないわね。ねえ、私の家に立派なステレオがあるんだけど、良かったら聴きに来ない?」
彼女はそう言った。僕はものすごく迷った。迷ったというよりはものすごく混乱してしまった。体温が3度ぐらい上昇したんじゃないかと思ったくらいだ。でも結局僕はその誘いに乗り彼女のマンションに行った。そして名目上であるステレオを見た。彼女の夫の書斎にあったステレオはマッキントッシュの真空管アンプにATCのスピーカーだった。そこから生み出される音は今まで聞いたこともないくらい上質で、優雅で、きめが細かく、感情のひとつひとつが摘み出されるみたいで、別の世界に連れて行かれるようだった。まるで彼女を抱いたときと同じように。
それから僕らはケータイの番号を交換した。そして週2,3度くらいは会うようになる。会うようになるといっても僕と彼女が会うということ、イコール、彼女と寝ることになる。それ以外には細々とした会話があるだけで、僕は会うたびに何度も彼女を抱いた。なぜ僕らが、こんな街で、こんなどうしようもない生活のなかでそんなことになったのか、ここでアイスカフェラテを飲んでいてもわかるはずがない。
そんなふうに僕と彼女の関係は始まることになる。そうして2年が過ぎ、何も変わらないまま僕は今、同じコーヒーショップの同じ席に戻っている。僕は同じようにアイスカフェラテを飲んでいる。なんの進歩もない。どうしてこんなところで僕と彼女は出会ったのだろうかと考えてみる。もちろん答えなんかない。それは偶然であり、同時に必然的な運命であり、生まれ持った遺伝子であり、記憶の再生だ。でもそんなことを言っていてもはっきりとはわからない。何ひとつ断言できない。
彼女はいかに日本のコーヒーがまずいかということを熱心に語る。それはいかに僕が下らない日々を送っているかというようにも聞こえる。
「イタリアでカプチーノを飲んでみるといいわ。それは、なんていうか、すごいのよ。ものすごいの。今までいかに自分がまずいコーヒーを飲んでいたのかはっきりとわかるのよ。今まで私が飲んできたコーヒーはどんなにひどいものだったかというのを、どんなに騙されていたかっていうことがはっきりとわかるのよ。それくらい違うの。原子の成り立ち自体が違うっていうくらい違うの。どんなに日本で有名なカフェで、値段の高いカプチーノを頼んでも足元にも及ばないっていう感じなの。あなたがイギリスに行きたいっていうように私にとってはそれだけでもイタリアに行く価値があると思うわ」
そんなことを言う彼女が、彼女が言うまずいコーヒーをわざわざ飲みに来たのかわかるはずもない。
僕はしがないロックンローラーという感じだったし、彼女はどう見ても僕とは次元が違うところで生きていた。彼女の血筋はいわゆる名門と呼ばれるもので、父親も立派な会社に勤め、母親は茶道と生け花の師範代の免許を持っていた。彼女の実家にはお手伝いさんがいて、お嬢さんとかいう貴族気取りの呼ばれかたをして育ったのだ。生まれたときから速く走ることを強いられ、そして速く走ることができる環境を与えられてきた伝統的なサラブレッドなのだ。さらにスピードを上げ、さらに新しい歴史的な記録を生み出す。それが彼らの宿命であり、ある意味では決められたレールの上を走ることを余儀なくされた呪われた人生なのだ。
僕と彼女の間にはそれなりに制約があった、と僕は思っている。彼女からそう言ったわけではないけれど、僕から彼女に連絡するということはなかった。彼女から着信やメールがあればすぐにかけなおすということはあったけど、僕の方から連絡をするということはなかった。それは、言うまでもなく、彼女は結婚していたからだ。
彼女はそのことについて触れたことがある。どうしてあなたから連絡してくれないの? と。彼女の夫は帰りが遅いらしく、夜の12時を回ることもしょっちゅうらしかった。ほとんど家にいないといってもいい。僕はそれを知っていても、どれだけ彼女を求めていても、ひたすら彼女からの連絡を待ち続けた。どうしてそんなことをしているのかもよくわからない。良心の呵責だろうか? そうじゃないだろうと思う。恐怖心だろうか? 僕は考えてみる。たぶんそうじゃない。じゃあなんだ?
“彼”がそのことについて以前にぐだぐだと言ったかもしれない。それは確かに的を射ていたかもしれないけど、僕は忘れてしまった。 “彼” の言うことは実は大して中身がないのだ。
僕の両サイドにいた参考書を読んでいた女性とサラリーマン風の男は店を出て行ってしまった。空いた隣の席には店員の女の子が何度もテーブルを拭きにやってくる。まるで僕にさっさと帰って欲しいと言わんばかりに。僕の目の前には飲み干したアイスカフェラテがあり、くしゃくしゃになってしまったストローの袋があり、吸殻が4本溜まった小さな灰皿が置いてある。その灰皿は吸殻4本が入るのがやっとという大きさだ。煙草4本分くらいしかここにいてほしくないということなのだろう。
カウンターの横の二人席の壁側に十代後半くらいの白いジャケットをきた女の子がウォークマンで音楽を聞きながら座っている。ちらちらと周りを見渡して、ときどき一ミリぐらいコーヒーを飲む。いかにも暇そうという感じだ。その女の子は僕のほうを見ないようにしながらも僕のことを意識しているような気がする。ときどき凝縮された視線を感じるような気がする。僕と同じようにどこにも行くところがないのだろう。僕の後ろ側にある席に3組の親子がやってくる。トレイにサンドイッチと飲み物を運んできて、がちゃがちゃと音を立て始め、「ここのコーヒーおいしいよねー」と大きな声で話し始める。
僕は音楽を聴いている携帯のボリュームを少し大きくする。
僕は彼女が僕のアパートに初めて来たときのことをほほえましく思い出す。それは冬の寒さが一日だけ和らいだ暖かい日で、僕らは最寄りの駅で待ち合わせた。彼女は一日だけコートを脱ぎ捨て、ジーンズにスニーカーというラフな格好でやってきた。昼過ぎごろだったと思う。僕が午前中に目覚めるということはめったにないからだ。駅で待ち合わせたにもかかわらず、周りの人に悟られないように僕らは離れて歩きながら僕のアパートに向かった。
「どうしていきなりトイレと台所があるの?」とアパートのドアを開けて彼女は言った。
僕はゆっくりとそのときの情景を思い出す。僕は彼女がアパートに来るということで、掃除をし、まとめて皿を洗い、部屋のなかで線香まで炊いて日ごろの匂いをかき消したのだ。よく考えてみればドアを開けていきなりトイレと台所があるのは確かにおかしいのかもしれない。ある意味ではいきなりいちばん汚いものを客人に見せ付けるようなものだ。でも僕が住める範囲での住宅事情ではそんなことは言ってられない。
「どうして? って言われても部屋の構造がそうなってるんだからしょうがないだろ」と僕は言った。「食って、クソして、寝るだけのところだよ。シンプルな生活をしてるんだ」
彼女は興味深そうに部屋を見回してなかに入った。僕はスリッパでもあったほうが良かったのかもしれないと思ったけど、僕の部屋ではわざわざスリッパを履いて移動するほどの距離はない。天井も低いし、トイレもシャワーも一緒になっている。シャワーがあるだけましだと彼女に言ってもおそらくわかってもらえないだろうから言わなかった。細胞の核のように僕は狭い中心にいるのだ。
高級なベッドであろうが、僕の狭い部屋の布団であろうが男と女がすることは変わらない。
「これは何に使うの?」裸の彼女が僕の部屋にある機材をいじって言った。
「それは、リズムを作る機械で……それは、音を録音して重ねる機械で……」と僕は説明した。「それぞれに役割があるんだよ」
「あのギターは?」
「ギターだけはアメリカ製の上等なものだよ。大学時代にビデオ屋でバイトして買ったんだ」
「ふーん、アメリカ製がいいの?」
「どうしてかわからないけど、やっぱり外国製品のほうがいいと思うよ。君がカプチーノについて言ったように全然違うんだ。ギターだけじゃなくて、ステレオも、車も、なんでもそうだよ。どんなに日本の技術が最先端だといっても全然違う。比べると格段に違うんだ」
「どうしてかしらね?」彼女は言った。
「この国は無駄というものが、つまり文化というものがまだ公認されてないからかもしれないね。日本のものが優れているところは、壊れにくいことだけだ。」
「壊れにくいところ?」
「喉を切り裂かれ、目を潰され、耳を塞がれてもまだ負けを認めたくないんだよ。細々と末永いものを選ぶか、壊れやすくても良いものを選ぶか、好き好きだけどね」
「ねえ、あなたっていつもそんなこと考えてるの?」
僕は考えた。どうだろうと?
「そんなことは、ない……と思うんだけど。でも考えることに縛られているかもしれない。楽しく生きてゆこうとそれなりに努力はしているつもりなんだけどね」
「それじゃあ、ケーキ食べよっか」
彼女はわざわざケーキを買ってきてくれていた。どこだか知らないけど、話題になったおいしい店にならんで買ってきたらしい。僕と彼女は裸のまま布団の上でそれを食べた。僕はケーキを半分ぐらい食べると彼女のお腹と胸に擦りつけ、それを舐めた。生クリームとスポンジと彼女の肌はひとつになって溶け合っていた。
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。