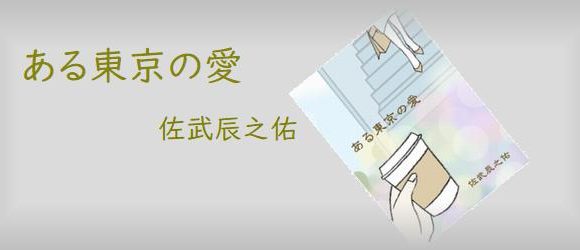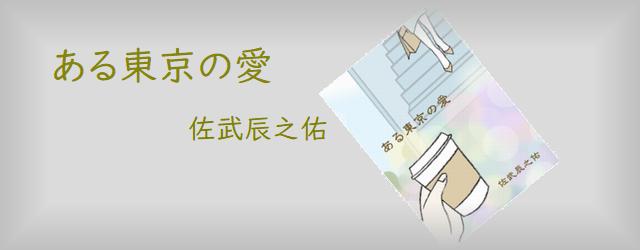
人々の波を押し分けてタカがやってくる。タカはモデルみたいに背が高くてかっこいいので遠目でも目立つからすぐにわかる。タカは僕の顔を見ると嬉しそうに笑う。ようやく僕は呼吸を取り戻したような気になる。暗い海底に潜っていてようやく水面に上がってきて胸いっぱいに空気を送り込んだみたいに。
「おう、遅れてワリイな」とタカは言う。
「べつにいいよ。どこいく?」
「居酒屋でいいだろ? 決めるのもメンドくさいしな」
僕は「いいよ」と答えていつもふたりで行く居酒屋に向かう。お決まりのコースだ。タカは仕事帰りみたいでスーツを着ている。片手にビジネスバックを持ち、短い髪はきちんと整髪料で整えられている。どこからどう見ても一人前の社会人だ。
今はこんな格好をしているけどタカは大学時代に一緒にバンドを組んでいて、その当時にはみんなぼさぼさの長い髪をしていた。そしてどうしてかわからないけど周りのメンバーは赤色のマルボロという煙草を吸っていた。何かの象徴的な効果を求めたのかもしれない。タカは当時プロになってもおかしくないぐらい神がかり的なギターソロを弾いていたけど結局は会社に就職した。会社に勤めだしてもう3年が経つ。今では主任だかチーフだかになってそれなりにうまく仕事をこなしているらしい。いくら上手いギターソロが弾けてもそれだけでは飯は食えない。
僕とタカは居酒屋に行くと生ビールを注文する。幾度となく繰りかえされる生ビールで始まる週末の夜。平和で、開放的で、限定された夜の幕開けだ。店のなかは週末らしく賑わっている。僕とタカはカウンターに腰を下ろしてビールを待つ。でも忙しいためかなかなかビールは運ばれてこない。
「ビールぐれえさっさと持って来いよな」とタカは言う。乾杯すると「あー」とお互いにうめき声をもらす。僕は仕事もしてないし、疲れるようなこともしていないけど、たまに外で飲むビールは格別においしい。
「おう、最近変わったことあったか?」とタカは言う。
「特にないね、そっちは?」
「ないよ。あればこんなところに来るはずねえじゃねえか」
「仕事は?」
「相変わらずだな」
「相変わらず、辞めたいのか?」と僕は聞く。
「そうだな。おまえは? なんかいい曲作れたか?」
「ダメだね」
「人妻は? まだ会ってんのか?」
「まあね」
「そうか……」
それだけ言うと、今日の会話は終わってしまったような気になる。改めて話すようなことなんてお互いにないのだ。僕らは食べるものを注文し、タカは一緒にビールのおかわりを頼む。タカはかつてバンドのメンバーの間ではメタル・レバー(鋼鉄の肝臓)と呼ばれていた。いつものように僕とタカが酔っ払ってくると音楽の話になる。そういう濃い目の話にたどり着くにはタカは生ビールを4杯流し込み、バーボンのロックの3杯目ぐらいに差し掛かってくるころだ。
「おまえはぜんぜんダメだよな? なあ? どうしてだと思う?」
「わかんないね」と僕は答える。僕もタカに合わせてバーボンのロックが手元にある。
「時代のせいにしててもダメだぞ、それはわかるよな?」
「そうだね」
「まあひどい時代だけどな」とタカは言う。「いつの世でもそうだけど、本物ってものを追いかけてても時代には受けねえんだよ。かといってろくでもないものも作ってられないしな。難しいところだよな」
タカの煙草はセブンスターに変わっている。僕もいつの間にかセブンスターになってしまった。お互いにストレスのバロメーターが上がったのかもしれない。
「結局どれだけ縛られているものを開放させられるかってことだろ? 聞いてる人の鎖を解けるかってことだろ?」
とタカは言う。タカは酔っ払っているとよくしゃべるので僕はほとんど聞き手になってしまう。
「それには枠があっちゃダメなんだよ。おまえはどうも形にこだわりすぎるんじゃないか? 最近作ったものは聞いてないけどさ」
「そういう風に作ってるつもりなんだけど」と僕は言う。
「違うんだな、これが」とタカはテーブルをノックする。
機嫌が良くなってきてリズムにのってきた証拠だ。タカは泥酔するということはめったにないけど、酔うと自分の考えを無理に押し付けるようなところがある。
「逆説的だけどな、枠を作らないようにするということは、だな、それ自体が枠なんだよ。わかるか? 矛盾だ、逃れられないパラドックスだ。堂々巡りで、悪循環だ。それで結局は自己完結になってしまうだけなんだよな、おまえの場合」
「じゃあ、どうすりゃいいんだ?」
「そんなことが簡単にできたら俺も今頃左団扇だよ。海外に別荘でも買って、毎晩朝までフィバーさ。情熱の夜に、かわいいセニョリータたちでな。ウエルカム・トゥ・プレイボーイ・ドット・コムって感じだな。とにかくやるしかねえんじゃねえか」
僕はタカが僕のためにそう言ってくれていることがわかる。それは嬉しく思う。確かに口で言うのは簡単だけど、それを曲という形に変えてしまうとすれば、どれだけ元々が輝いていたとしても空気に触れるとただの石ころになってしまうのだ。それからはどこどこのバンドの誰々がどうなったとか、この間買ったアルバムは良かったとか、発売されたばかりの新しい機材についてとか、そういう当たり障りのない話をする。
店を出るときに勘定はタカが払ってくれる。僕は一旦店を出てから割り勘の分を渡そうとするけど、
「いいよ、いいよ、出世払いでな」とタカは言う。僕は申し訳なく思うけど、友人の行為をありがたく受けることにする。僕も、おそらくはタカも、僕が出世払いなんてできないことを知っている。
タカと別れてアパートに戻るとすぐに曲を作ってみる。機材の電源を入れ、ギターのチューニングをする。僕はできる限り、僕自身に戻ろうとする。素直に心を開き、僕の感じるものをリズムに乗せてゆく。コードを崩し、スケールと呼ばれる音の並びをすべて忘れる。
ひとつの音を作るとリズムは左右に揺れ、ときには残酷に、ときには甘く、僕が鏡のように曲のなかに映し出される。調子の良いときはリズムが僕に拾われることを待ち構えているような気がする。いろんな色をリズムと一緒に渦のなかに流し込んでゆく。僕は自分がその渦の中心の軸であると思い込ませ、リズムのなかを、僕自身のなかを進んでゆく。ただここにあるものを時間という横軸に置き換えてゆくだけだ。それはスリリングな冒険であり、未知の世界へと身体を沈める探求でもある。すべての表現を捨て、沈黙から始まり、沈黙で終わる。曲と自分の間に一定の距離を保つ。そうして作っているときは僕なりに良いものができていると思う。でも次の日完成したものを聞いてみると、ゴミ箱の蓋を開けたような気分になる。
ごくたまに気に入ったものができるときがある。そういうときの一日の始まりは爽快なものだ。鳥たちと共に歌い、大空を飛び回る。でもしばらくすると気に入った曲もただの石ころになってしまう。
僕は振り出しに戻ることになる。僕は合わせ鏡という壁にぶち当たりそこから逃れられない。ドアをノックしてみてもそこから返事はない。
僕もいろいろと試行錯誤を繰りかえしてみる。このアパートで大きな音で音楽を鳴らすことはできないので僕は環境を変え、スタジオに入って耳がキーンという残響を残すぐらい大きな音で曲を作る。それでも良いものはできない。
気分転換のために公園に行ってしばらく散歩をする。木々をじっくりと観察し、育つまでにかかった時間を想像して僕も光合成の旅に出る。季節の風の匂いを身体に染み込ませ、人々が気持ちよく歩いている姿をのんびりと見つめる。スポーツウェアーに着替えてジョギングをする。それから無心で部屋に帰って曲を作る。
彼女とセックスしてからすぐに曲を作ってみようと思う。でもセックスした直後というのは精神的に満たされていて何かをしようという欲求が湧いてこない。
六缶セットのビールを買ってきてぐでんぐでんに酔っ払ってからギターを弾いてみる。
30分ほど瞑想し、空っぽになってからリズムを刻んでみる。美術館、博物館に行ってみて感性を刺激してみる。たまには早く寝て早く起き、清々しい朝の空気のなかで、新鮮な太陽の下で曲を作ってみる。時には僕の耳に付いた贅肉をそぎ落とすために他人の作った音楽は一切聞かないことにする。生命維持のために最小限度の音の中で暮らすことにする。雨や風の音、足音、歯を磨く音、皮膚が擦れあう音。そうして僕自身の音を探し出す。
それでも同じようにゴミしか生まれない。
どれだけあがいてみても、僕はどこへもいけないんだと思う。何もかもがダメな日は、ほとんど毎日がそうだけど、眠りの中に救いを求めるように布団に入る。
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。