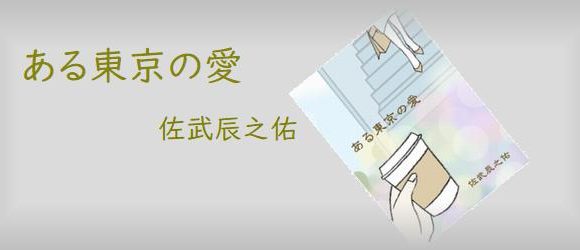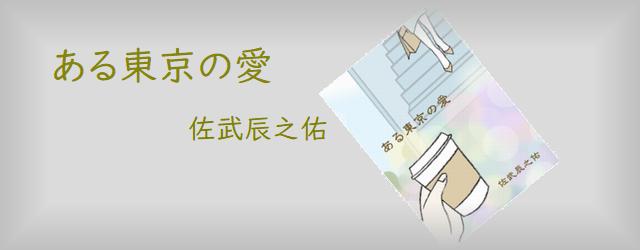
「ライブか。まあまあってとこじゃないか。どうだった?」
「俺としてはな」タカはようやくまともな表情に戻る。「方向性は間違っていないと思うよ。少なくとも今日の出演者のなかじゃいちばん良かったと思う」
「エリカちゃんのことか?」と僕はいじわるを言ってみる。
「もうやめろって言ってんだろ!」とタカは言う。「しつこいんだよ」
僕はこうやってからかうのが好きなのかもしれない。
「大事な音楽の話だろ。音楽の話いー」とタカは言う。
「ああ、音楽の話な」僕は諦めて話を戻すことにする。「でもダメだな。気に入ったものはできないし、実際に良くなってきてるのかもわからない」
「おまえな、気に入ったものなんてできるはずないだろ。そんなものができたらそこで終わりだよ。自分のやってることがわかったらそれ以上何も出てこないぞ」
「それはそうかもしれないな」結局いつものパターンでタカがしゃべり、僕は聞き手になってしまう。
「俺たちはただの工程ってものしか作れないんだ。それでいいと俺は思うよ。要するに、一瞬の間に完璧な不完全ができればいいわけだろ。まあ、それが売れるかどうかは別にしてもさ。レコード会社とかには連絡してないのか?」
「インターネットに載せてある曲もある。たぶんダメだと思うけどね」
「宝くじだって当たるかどうかはわかんねえけど、買わないことには可能性もないわけだろ?」
「そりゃあそうだけど、宝くじなんて当たる気がしないね。もしかしたら宝くじのほうが確率はいいかもしれない」
「なあ、そんなこと言ってもしょうがないだろ。少なくとも俺はおまえの音楽はいいと思うよ。確かに時代には合わないかもしれない。みんな新しいことなんて知りたくないのさ。そんなものを抱え込んで混乱するのが嫌なんだ。適当に左から右に流れていって、暇が潰れりゃそれでいいんだ。自分の欠落を見つめなくてすむならな。でも、ミュージシャンはまだましにしても画家なんてひどいもんだぜ。その画家が死んでから誰かが墓をほじくり返して、この人はすごい、ものすごい作品だ、なんて言われるんだぜ。じゃあ、生きている間はどうなるんだ。変人扱いされて、貧乏で金がなくて、キャンパスも買えないからペラペラの紙に描いてる画家はどうする?」
「まともに働いたほうがいいってことか?」
「違う。そういうことを言ってるんじゃない。働きたければ働けばいいじゃないか。俺が言ってるのはそういうことじゃないよ」
「ありもしない希望を持てってことか?」
「それも違う」とタカは言う。「そんなものは俺も持てない。だからこうゆう状況になってるんだろ?ヒューマニズムとかリアリズムとか時代がどうのこうのとか、ごちゃごちゃ言っても結局なんの足しにもならないんだ」
「じゃあ、どうゆうことだ?」
「そんなこと俺に聞くなよ。誰かが出した答えなんて結局誰かのものでしかないんだ。俺は俺だよ。そんなものに理由もクソもない。俺はおまえにはなれないし、おまえも他の誰にもなれない」
「なりたくもないけどな」と僕は言う。
「そりゃ、まあ、そうだな」とタカは答える。
そうやって答えの出ない話が延々と続く。タカはバーボンを飲み進み、僕はちびちびと付き合う程度だ。終電が近くなってくると店を出る。なんとか終電の一つ前の電車に乗りたいと僕は思う。こんな日曜の夜遅くでも終電は込んでいるからだ。
タカは勘定を払ってくれて、一緒に駅に向かう。僕は別れるまえにもう一度エリカちゃんのことでからかってみようかと思うけど止めにする。世の中の流れは速く、あっという間に熱は冷め切ってしまう。
次の日の月曜日から僕は仕事探しをする。僕はコンビニにいってまとめて求人誌を買ってくる。アパートに戻ってそれをテーブルの上に並べ、にらめっこをする。僕には特にこれといった業種の希望はない。とにかく早く金が貯まって、できるだけ早くこちら側の生活に戻ってくることを望んでいるだけだ。いつまでそれを繰りかえすのか、繰りかえしてそれでどうなるのか、といったことはひとまず脇に置いておく。そんなことをいつまでも考えていても金は減る一方だし、働くこともできなくなってしまう。
でもどれだけ求人誌のページをめくっていても、気が滅入ってくるだけだ。インターネットでも求人のページを覗いてみて、仕事紹介のページで個人登録をすませる。
夕方前に突然ケータイが鳴る。着信はみたこともない番号なので電話に出ないでおこうかと思うけど、しつこく鳴り続けるので出ることにする。
「もしもし、○○さんでしょうか?」と僕の名前を言う。聞いたことのない女性の声なので「そうですけど」と怪しみながら答える。
「今日インターネットで我社のページに登録をしていただきましたよね?早速なんですけど、ご紹介できるお仕事がありますのでお電話差し上げました。今、お時間よろしいですか」
「はい」と僕は答える。こうゆう事務的で、礼儀正しい電話をしばらくしていないので僕は緊張してしまう。
「今何かお仕事はしてらっしゃいますか?」
「いいえ、していません」
「それでは、ご足労ですが一度わが社のほうに来ていただけないでしょうか?インターネットでは正式な登録にはなりませんし、お仕事のほうもできればこちらでお話したいのですが?」
僕は一瞬どうゆうふうに答えていいのかわからなくなってしまう。とりあえず「よろしいです」と答えてしまう。よろしいです?それは僕のせりふではない。けっこうです、と答えるべきだったのだろうか?でもけっこうです、ということは断っているふうにも聞こえるし……。
「それではいつごろお時間よろしいですか?」相手の女性は躊躇なく話を進めてしまう。
「僕としてはいつでもいいですが……」
「それでは、明日の3時にオフィスのほうへいらしていただけませんか?」
「大丈夫です」と僕は答える。「お伺いいたします。よろしくお願いいたします」ようやく社会的なカンが戻ってきて僕はそう答える。
「オフィスの場所はおわかりになりますか?」
「インターネットで調べますので、大丈夫かと思います。明日の3時にお伺いしまう」
僕は焦って舌を噛んでしまい、「します」のところが、「しまう」と言ってしまう。
「それでは明日お待ちしております」相手の女性がそう言って電話が切れる。
なんだかわからないけど、とにかく求人誌とのにらめっこは一旦休戦ということになった。僕は明日のためにスーツを着てみる。ネクタイを締め、ワイシャツを着る。クリーニングから戻ってきたままになっていたビニールの袋を取る。それから鏡の前に立つ。そして、なんだコイツ、と我ながら思う。でもそういう違和感を、時間をかけて消してゆく。鏡の中の自分をさまざまな角度から眺めてみて、社会と自分とを少しずつ繋ぎ合わせてゆく。どこかから何かを切り取り、僕のなかに貼り付ける。ズボンのポケットに手を突っ込んでみて、ジャケットを何度も着たり脱いだりして身体に馴染ませる。スーツのままトイレに行ってみて、おしっこをしてみる。鏡の前で煙草を吸ってみる。僕じゃないみたいに見えるけど、最初の違和感は少しずつ和らいでゆく。何事も慣れなのだ。彼女が見たらなんていうだろうと僕は考えてしまう。おそらく笑われるだろう。
僕はふと作りかけていた曲のことを思い出す。念のため仕上げてインターネットに載せておこうかと思う。でもスーツ姿の自分を見ているとそんな気は失せてくる。僕はもうスーツを着てしまっているのだ。今さらどうにもならない。僕は面接に行く前に半年振りに美容室に行き、髪の毛をカットしてもらう。おかげでどこか別の惑星から連れてこられた宇宙人みたいになった。
次の日の3時に会社に向かう。出迎えてくれたのは昨日電話をくれた女性と同じみたいだ。小太りで、細い目をさらに細めながらひきつった笑いをする。30台半ばから後半ぐらいだろうと思う。その女性が僕の担当になっているみたいで、小さくバロック音楽が流れる清潔なオフィスでいろいろとテストをさせられる。一般常識や、マークシートの性格診断、パソコンがどれぐらい早く打ち込めるか、それから僕の職歴を聞かれる。
「何か資格のようなものはお持ちですか?」と女性は言う。
「いいえ、持っていません。ギターの早弾き初段は持ってますけど」
「それは、履歴書には書いてないですね」
僕の冗談は全く通じなかったみたいで、それが冗談だとわからない相手の女性は僕と僕の書いてきた履歴書に交互に視線を送る。僕を異邦人のような目で見つめている。僕はもう冗談は止めておいたほうがいいなと思う。
「今までどのようなお仕事をなさってきましたか?」
僕は自分の職歴を話す。大学を卒業した後の工場の夜勤や、レストランのウエイター、ビデオ屋の店員、短期のリゾートバイト、トラックドライバー、その他もろもろ。相手の女性は履歴書に書いてあるはずなのに、仕事をしていた正確な場所と時期を聞いてくる。僕はそんなことどうでもいいような気がするけど、なんとか思い出しながら詳しく話す。
「今回ご紹介したいのは、簡単な電話のお仕事なんです」そう女性は言う。
「簡単な」というところが強調されて聞こえるような気がするけど、僕は続きを待つことにする。
「会社のほうから電話をかけるリストをお渡ししますので、そのリストに従って電話をしていただくだけです。経験がなくても誰にでもできるお仕事ですので、ぜひやってみられませんか?」
「はい」と僕は答える。
「経験がなくても誰にでもできる」という部分がまた引っかかるけど、僕は「はい」と答えることにする。いちいちそんなことで引っかかっていたら働くことはできない。
相手の女性は契約内容や仕事条件、そういったものが書かれた書類を出してきて僕にサインをさせる。書類にはすでに僕の名前が書かれている。その書類は僕が会社に来る前から机の引き出しに入っていて、おずおずと女性が引っ張り出してきたものだ。僕がここに来る前から、テストや質問を受ける前から、それはあらかじめ決まっていた運命のように思えてくる。僕は運命を提示され、それを受け取っただけというような格好になる。
運命の歯車は僕の知らないところで回り続け、次の歯車をしっかりとくわえ込み、大きな破壊的な音を立てて次の歯車は回り始める。そんなことが起こっているなんて僕には知る由もない。
「突然で申し訳ないですが、明日からさっそくお仕事よろしいですか?」相手の女性は言う。
「大丈夫です」僕がそう言うと、勤め先の地図を渡され、仕事の心得や、契約上の規定、そういった書類も一緒にファイルに挟んで渡してくれる。
「良く読んでおいてくださいね」最後に相手の女性はそう言って、形式的で親密さを与える微笑を僕に投げかけてくれる。
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。