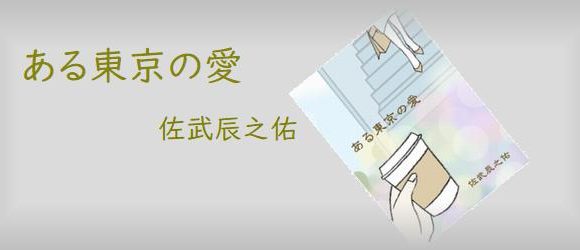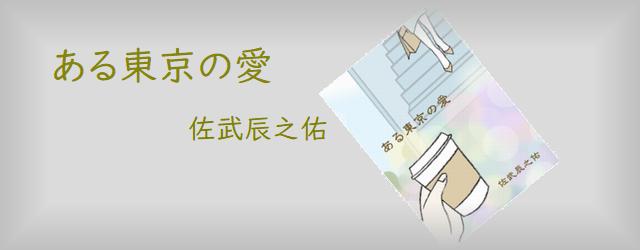
「お嬢さん」とタカはその子に言う。
「そのお嬢さんっていうのやめてくれる?」とすばやく女の子は言う。
「ごめん、ごめん、名前はなんていうんだっけ?」とタカは言う。
「エリカだけど」エリカはおもしろくなさそうに答える。
「いきなりエリカちゃんがアイデンティティなんていうもんだから、ちょっとびっくりしちゃって」
「なんかモンクあんの?」とエリカは言う。周りのみんなはちょっとやばいことになってきたなという雰囲気を察知し始めている。
「あんたみたいなのはね、人を見下したような男は結局何もできないのよ」
「それは自分のことを言ってんのか?」とタカは言う。
そう言われたエリカの顔は怒った顔になる。
「まあ、まあ、やめとけよ、タカ」とシンジが言う。「エリカちゃんもごめんな、悪い奴じゃないんだけど、とにかくストレートなんだよ」とシンジは落ち着かせようとして手を上下に振る。
「あんたみたいのがいるからね、世の中異常なのよ」とエリカは続ける。「あんたみたいな男が大勢いるから人間の尊厳が奪われていくわけでしょ。芸術が堕落してゆくわけでしょ、ね、ね?」
エリカは「ね、ね?」と言って周りの女の子に同意を求める。でも周りの女の子たちは話についていけないといった感じで曖昧に頷く。
「君の頭がいいのはわかったよ」とタカは言う。「だから別にいいじゃないか。君の頭がいいのはみんなもうわかったし、それ以上君の講義は聞きたくないんだ」
「何よ、その言い方」とエリカは言う。「なんかモンクあるんでしょ?」
そう言われたタカはしばらく黙っている。みんなも黙ってタカを見つめている。
「じゃあ、言うけど、君みたいに適当にアイデンティティとか芸術が堕落していくという人間がいるから安っぽくなるんだよ。そういう人間がいちばん物事をしっかりと見ないんだ。何も見てない。見ようともしない。何も認めようとしない。ただ枠のなかのぬるま湯にどっぷりと浸かっているだけじゃないか。そこから出ようともしない。疑いもしない」
「もうやめとけって、タカ」今度はユウが言う。それでもタカは続ける。
「適当な横文字や曖昧で堅苦しい言葉を使えば頭がいいと思う。それはただのファッションでしかない。難しいことを言えば、人が知らないような単語を使うことで自分が偉くなったようなつもりになっている。はっきり言ってそういうのはクソだよ。ゴミ以下だ」
「バーカ、あんたなんてただのバカじゃない」とエリカは言う。手元にあった割り箸をタカに投げつける。エリカは泣き出しそうな顔をしている。
「もうやめてください」とリエが言う。「エリカもうつ病チックで大変なんです」
「何がうつ病だ!」とタカは声を大きくして言う。「こんな時代じゃ当たり前だろ。俺だってうつ病ぐらいなったよ。安定剤飲んでチンポも立たなくなったよ。それぐらい当たり前なんだよ。死んで救われるぐらいなら俺だって何度でも死んでるよ。自分だけがつらいと思ってんじゃねえ、自己家畜化オンナ!」
僕も止めようと思うけど、もう勢いがついていて止められる段階ではないな、と思う。タカはライブ中にちょっかいをかけてきた若い男にギターを投げつけて警察沙汰になったことがあった。
「頭のいいエリカちゃん、自己家畜化って知ってるか? おい、知ってるか? 何だよ、そのバッグは、それにアホみたいな格好しやがって。モノの価値にすがらないと生きてられないんだろ。周りについていかないと、そんなもんで自分を埋めないと不安なんだろ。別に空っぽでいいじゃねえか。それしかねえじゃねえか。そんなもんも受け入れられないくせにガタガタいってんじゃねえ!」タカは怒鳴りつけるように言う。
エリカは泣きながら席を立って外に飛び出してしまう。リエも、その他の女の子も追いかけるようにして店を出てゆく。タカが大声を出し、女の子が走るようにして出て行ったため店員が覗き込んでくる。席は静まりかえってしまう。
「タカ、おまえが悪いよ」とユウが言う。いつもメンバーのなかで揉め事があるとユウが取り仕切った。いかにもベーシストらしい役柄だったけど、バンドを組んでいたときもユウがいなかったらシンジとタカの揉め事ももっとひどいことになっていたと思う。
「相手はハタチそこらの女の子じゃないか」とユウが言う。
「なんだよ、いつもの女性至上主義かよ。そうやってなんでもわかっているように突き詰めないから俺たちもダメになったんだろ」タカが言う。
「そういうことじゃないよ。今そうゆうことを言ってるわけじゃないだろ?」ユウはあくまでも冷静だ。「とにかくエリカちゃんには謝ったほうがいいよ。おまえもそれぐらいわかるだろ?」
「さすが大人って感じッスね」とリエの彼氏が言う。
タカは彼氏のほうを一度睨んで、煙草を手にとって火を点ける。席に残った男たちはみんなタカをじっと見つめている。
「わーかったよ。確かに俺が悪かった」タカはそう言う。
「おまえも追いかけてこいよ。おまえの責任だからな」ユウがそう言うとタカはしばらく煙草をふかしていたけど、のそのそと立ち上がって店を出てゆく。
「リエに電話してみましょうか?」リエの彼氏がそう言ってケータイを取り出そうとする。
「大丈夫、タカもそこまでアホじゃない」とユウが言う。
「さすが、カンロクって感じッスね」
僕とユウ、シンジと彼氏はそのまま騒がしい居酒屋に残される4人ともしゃべらずに誰かが戻ってくるのを待つ。20分ぐらいしてようやくタカとリエが戻ってくる。
「みんな帰っちゃった」とリエが言う。
「とりあえず出ようぜ。俺が払うからさ」とタカが言う。
タカが会計を済まして、居酒屋を出る。
「どうなったんだ?」ユウがタカに聞く。
「なんとかなったよ。ケータイの番号も聞いたし、今度改めて会う約束もした」
タカがそういって解散になる。
リエが僕のところに寄ってきて、
「いろいろとありがとう。元気でね」と言う。
僕も「こっちこそ、ありがとう。元気でな」と言う。
リエは彼氏と肩を組んで仲良く帰ってゆく。ユウとシンジもそこで別れる。
「それじゃあ、もう一発行くか?」とタカが言い、僕とふたりで別の居酒屋に向かう。結局、いつものコースに戻ってきてしまう。
「俺がおごるからさ」
「べつに割り勘でいいよ。先週もおごってもらったし、今も払ったじゃないか」
「水臭いこと言うなよ」とタカは僕の肩を抱く。「金なんて使うときには使わないと、心が貧しくなっちゃうんだ」
僕はまた申し訳ないなと思いながらもタカと別の居酒屋に行くことにする。タカが選んだ店は騒がしいチェーン店ではなく、やわらかな間接照明が灯っている静かで落ち着いた雰囲気の店だ。僕らはカウンターの席に並んで座る。
「いやあー、今日はまいったな」とバーボンのロックを一口飲んでタカが言う。「俺も年くってきたのかもしれない。仕事で疲れてんのかな?」
「それでどうなったんだ、エリカちゃんとは?」
「ああ、とにかく平謝りだ。俺が悪いわけだし、そうするしかないもんな」
「それで?」
「一応許してもらえた。だいたいあんなこと言う子に限って、ほんとはものすごくまともなんだよ。異常っていうのは、ある意味では正常な反応ってことだろ。まともだから、いろいろ考えたり、悩んだりするわけだろ? 元々は純粋なんだよ。こんな街でなんの悩みもなく平気でいられるような奴のほうがよっぽど異常だよ」
「それで? そういうことを言ったのか?」と僕は聞く。
「そんなこと言うわけないだろ。そんなまた頭でわかったようなことを言えば逆効果さ。特に若い女の子だろ。難しい年頃なんだよ、お互いに」
僕もバーボンを飲んでいるけど、あまり注文しないことにする。いくらおごりだといわれてもそれなりに遠慮というものがあるからだ。もしかしたらそうゆ(い)うのは日本人独特の下らない美徳なのかもしれない。じゃんじゃん注文して、ほとんど残して、経済に貢献するべきなのかもしれない。でも僕はそんなことはしない。
「もしかしたら結構気が合うんじゃないか? エリカちゃんと。今日いた女の子のなかじゃいちばん綺麗な子だったし」と僕は言ってみる。色気がなかったということは言わないことにする。
「あ? 俺が? あのエリカちゃんと?あのファンキー・モンキー・ベイビーとか? そんなことになったら会うたびに国際サミットだよ。赤コーナーと青コーナーに分かれてな。血みどろの極秘中継になりかねない」
「でも、今度デートするんだろ?」
「まあ、付き合いだよ、付き合い。最後のほうは急に女らしくなったから、機嫌取っとかないとな」
「へーえ」と僕は言う。
「なんだよ」とタカは僕の顔を見る。「そんな顔すんな! 別に変なことはしないよ」
「タカも久しぶりにメスの匂いに在りつくってわけか」
「なに言ってんだ」とタカは慌てる。「そんなことしねえって言ってんだろ。おまえはいつも低俗なんだよ。いやらしいことばかり考えやがって」
タカは5年も同棲していた彼女と別れて以来、全く浮いた話というのを聞いたことはなかった。本人はそういうことを言わないけど、それが引き金になってギターをやめてしまったんだと僕は思っている。
「そういえば、そうだ! 今日のライブどうだった? 手応えはあったか?」
「無理に話を変えなくてもいいよ。気に入ったんだったら、そう言えばいいじゃないか」
「違うって言ってるだろ!」タカは少しムキになって言う。「ライブだよ、ライブ。今日はどうだった?」
僕はわざと間をおいてタカの顔を見る。そして成るように成るか、と思う。
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。