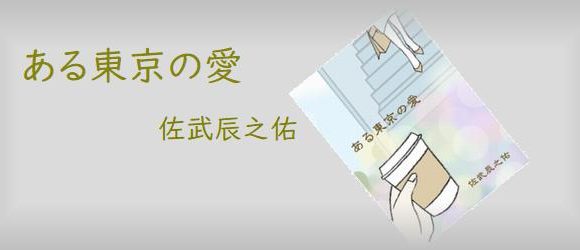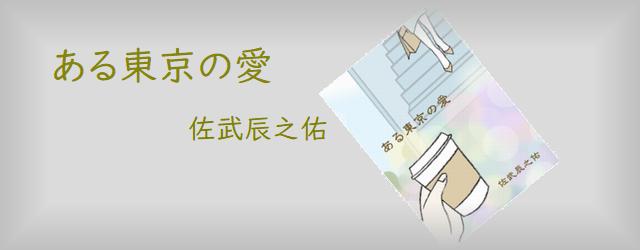
それから約束の金曜日まで僕はもうろうとした意識のなかで過ごす。仕事に行っているときはまだいいけど、アパートにいるとため息ばかりが出てくるようになる。音楽は耳の奥まで届かないし、だいいち音楽を聴こうとも思わなくなる。ご飯も食べる気がしなくなるし、そもそも作る気がしない。テレビも見たくなんかないし、友人からの連絡はうっとうしく思えてくる。
僕はもんもんと考える。でも考えても考えても何も出てこない。考えても考えても答えなんか出てこない。それはわかっていても考えてしまう。
彼女のことを考えているつもりでも、ときどき仕事のことが頭を過ぎる。僕はどうして仕事のことなんか考えなくちゃいけないんだと思う。でも知らないところからそれは現れ、僕の頭を殴り、顔を上げるとその姿は見えなくなっている。僕はまた彼女のことを考える。そうすると彼らがまた頭を殴りに来る。
僕はいっそのこと仕事を辞めようかと思い始める。たとえ僕が仕事を辞めたとしても、何も変わらない。僕の問題が解決するわけでも、この街の問題が解決するわけでもない。僕が仕事を辞めた後には誰かが入ってきて僕の代わりを務める。そこに一時的な穴が空いたとしても、その調和は変わることはない。この街に鼓膜が破れそうなぐらい響き渡っている不協和音が今さら少しぐらい大きくなったところで誰もそんなことには気が付きもしない。
僕は身体に染み付いた習慣のまま電話する。いつも通りのペースで仕事を続ける。何も考えないようにする。でもどこか遠くで、僕が見ることもできないような遠くのどこかで僕は考えてしまっている。
しかし、そこには何かが足りない。僕の感じることが、感じなくてはいけないことが、元々なにかそこにあるものが、あるべきものが、そこにはない。僕はもっと何かを感じなくてはいけないんだ、と自分に思い込ませる。
僕は考える。そもそもの原因はなんだ? と。どうしてこういうことになったんだ、と。
僕はさらに、深く、じっくりと物事を眺めるように考える。
元々の原因はなんだ?
何かを表面的に解決したところで、それは本当の解決とはいえない。ただ誤魔化しているだけだ。芽が芽生えたところ、根の先端まで穿り返さないと、問題は解決しない。
僕はさらに考える。なにが原因だ? いくら考えても答えは出てこない。考えても、そこに答えはない。考えても、そこに、こたえは、ない。
金曜日の朝に起きると布団を押入れに入れ、顔を洗って歯を磨く。昨日の夜に飲んだビールとウイスキーのグラスを洗い、お湯を沸かしてコーヒーを入れる。テーブルに座ってコーヒーを飲みながらケータイを見つめる。でもケータイを見つめていても何かが起こるわけじゃない。ケータイの時計は9時13分を示している。
僕は彼女にメールを送る。
「今日、会える?」と。
僕は彼女からの返信を待ちながらコーヒーを飲み、煙草を吸う。煙草が燃えるのをじっくりと見つめ、そこに何かしらの意味を探そうとする。煙草の煙は僕の指を這うようにして部屋のなかに燃え広がってゆく。たいした意味はない。ただ燃えているだけだ。
ケータイが鳴って彼女からのメールが来る。
「会えるんだけど、今日はどこか外で会わない?」とある。
僕は彼女と僕の家の中間ぐらいにある駅を指定して、12時でどう?とメールと送る。彼女から了解のメールが来る。
僕は部屋に掃除機をかけて、テーブルを拭き、それからシャワーを浴びる。
浴槽のカーテンを閉め、狭い場所に挟まれたまま僕は髪と身体を洗う。浴槽の排水栓を閉めてあるので流れたお湯は僕の足元に溜まる。僕は溜まったお湯を温めなおし、身体をお湯のなかに埋める。僕の髪の毛や垢が浮いていて汚いけど、元々は僕のものなのだ。あまり気にしないことにする。僕は湯船に浸かって昔のことを思い出す。ほんの少し昔のことだ。
季節は春だったと思う。春や人々が何かを求める匂いが風のなかで踊っていた。でも僕はそんなものに気を留めてもいなかった。何かが決定的に崩れ落ちることもなく、風の音さえ僕の耳には入らなかった。世界は今やっと扉が開けたように僕の目の前に広がっていた。あるものはこれ以上ないぐらい純白な衣を身にまとって光り輝いて見え、それを近くで見ようと誰もが人々を押しのけ、最前列めがけて前へ前へと進んでいった。それを勝ち取ったものは高らかに大声をあげ、手に入れたものを頭上にかざすと観衆の誰もがそれに釘付けになった。
そのレースは休むことなく、足が折れようが眼が潰されようが周りを見れば誰も彼もが走り続けていた。僕らは自分の持ち得ることのできる意味を大事な卵のように抱きかかえ、いつの日かそれが何かに変わって僕らを救ってくれるだろうと信じていた。そんなものがただの石ころだということに気がついた者から目の前にいる最初の敵に向かって思いっきり石を投げつけた。そしてそれが合図となり、人々が永遠と繰り広げてきた革命への参加となった。
浴槽のお湯はシャンプーや石鹸のために白く濁っている。そこにはついさっきまで僕の一部であったものが浮かんでいる。僕は両手にお湯を掬って顔にかける。そして、そう、これこそが僕の失っているものなのだと思う。
お風呂から上がると僕は服を着て出かける準備をする。彼女と外で会うのは久しぶりのことだ。いつ以来なのかも覚えていない。仕事を始めてからほとんど彼女に会っていないので、彼女に会うこと自体すごく久しぶりのことだ。
目的の駅に付くと改札を出て、階段を下りたところで彼女を待つことにする。僕は壁にもたれながら階段を下りてくる人の顔を眺めている。サークル状になったバスの停留所には何台かのバスが停まり、人が乗り降りしているのが見える。スーツを着ている中年のおじさんが拡声器を使って大きな声で演説をしている。僕はケータイを取り出して時間を見てみる。時間は11時42分を示している。風が強いせいか空は真っ青に晴れ上がっていて、まばゆい太陽の光が街中を照らしている。気持ちの良い一日だ。
階段を見上げながら人々が横を通り過ぎて行く足音を聞いていると突然これはどこかで見たことがある風景だと思った。今僕の目の前で起こっているはずのことなのに、これはどこか別の遠いところで見たことがあるような気がする。これはすでに起こってしまったことであり僕は自分の記憶を再生しているだけのような気がしてくる。
僕はケータイを取り出して時間を見てみる。時間は11時42分を示している。
そう言えば、あの時も11時42分だったような気がする。あの時も僕はここで彼女が来るのを待っていたような気がする。でも、あの時とは、一体いつのことだろう? 僕はあの時も彼女を待っていたはずだ。彼女は現れたのだったろうか?
彼女は階段を下りてきて僕に微笑んだような気がする。僕はその微笑で生き返ったような気になった。でもそういう気がするだけで、本当に彼女は現れたのだろうか?
時間の感覚がおかしくなっている。パズルがばらばらになっている。僕はこんなところで何をしているのだろう?
人々は僕の横を通り過ぎてゆく。僕は階段を見上げてみる。そこには見覚えのある風景がある。何かがおかしい。何が、どう、おかしいのかはわからない。でも何かがおかしい。
僕は街のなかにいる。でもここは一体どこなのだろう?僕はなぜこんなところにいるのだろう?
人々は僕を横目で見ながら通り過ぎてゆき、バスはクラクションを鳴らす。僕の記憶が再生されている。僕は叫び声を上げそうになる。何かが間違っているんだ、と。
僕は記憶のなかの現在にいる。
何かが失われ、間違っている。でももう間違いを正すことはできない。僕は固いコンクリートにしゃがみ込む。気が狂ったような意味のわからない声が聞こえる。旋律は失われ、記憶を亡くした僕の耳に届く。
何かが間違っている。僕の感じることのできる何かが、僕の何かが間違っている。僕はこの街に包まれて、聞こえない音を必死で探し求めている。
あとがき
この「ある東京の愛」という作品は私がまだ日本に住んでいたころ、十数年前に書いた物語です。当初はこの最終章のタイトル「記憶の中の現在」の題名をつけていたのですが、kindle化するときに少し修正しタイトルも現在のものに変えました。
この作品のkindle版が地球丸編集部の目に止まり今回掲載させていただく運びとなりました。
これを機に続編を執筆しようかと思い悩むところではありますが、これを書いたのは随分と昔のことですので、一旦は保留とさせていただき、続きが書けるようであればまた別の機会にて発表させていただきます。
今回私の作品を我慢強く修正していただいた編集部の皆様へもこの場を借りてお礼を申し上げます。
2021年2月17日
佐武 辰之佑
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。