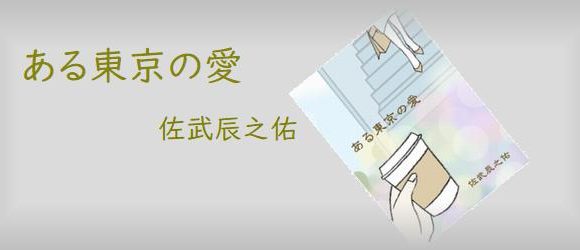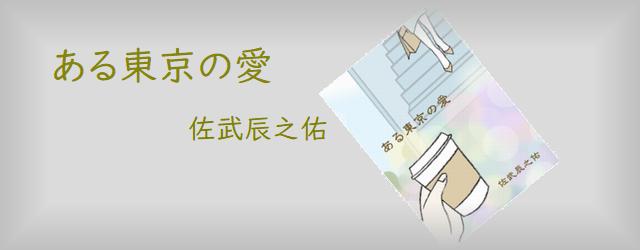
火曜日は彼女のマンションへ行き、金曜日は彼女が僕のアパートへやってきた。僕はライブが終わったら来週から働くことになると思う、と彼女に言う。
彼女は「そうなの」と答えるだけだ。
僕が働き始めると彼女と会うことは難しくなる。それでも彼女がそれについてどう思っているのかということは言わないし、僕も聞かない。
あっという間に週末の日曜日がやってきて、僕のライブの日になる。昼過ぎにライブハウスにいってリハーサルをする。狭いライブハウスでは他の出演者たちがまばらにいて、ライトの試験なんかが始まっている。僕とリエはステージに上がり、誰も観客がいない暗闇にむかってリハーサルを始める。音のバランスやマイクの音量、機材のセットの確認をする。調整が終わると「本番よろしくお願いします」とマイクでライブハウスの人に言う。リエも「お願いします」と言う。
ライブハウスで働く髭の生えたおじさんは「ハーイ、よろしくー」と返事をしてくれる。このおじさんは僕のことを覚えてくれていて、時々声をかけてくれる。相変わらずだな、と言って僕の背中を嬉しそうに叩いてくれる。でも評論めいたことは言わないし、みんなから慕われているみたいだ。
5時半に開場になり、6時から最初のバンドの演奏が始まる。僕とリエは5バンドあるうちの4番目だ。5時半に開場になっても薄暗いライブハウスは全然人が集まっていない。ちらほら壁に寄りかかっている人もほとんどはバンドの身内やその友達といったところだ。みんな遠慮がちにステージから離れた闇のなかに腰を下ろし、今演奏しているバンドの身内だけが付き合いといった感じで最前列に短い列を作る。
僕とリエもテーブルが置いてある後ろのほうに座って演奏を見ている。そのうちちらほらと僕とリエの身内がやってくる。最初に来たのはリエの彼氏で、痩せていて歩くシルバーアクセサリィのカタログのような男だ。
「どうも、コンチハッス」とリエの彼氏は僕に挨拶をする。僕も適当に返事をする。演奏がうるさくて声が聞こえにくいからだ。彼氏はリエの耳元でなにやら話を始める。それからふたりでどこかに出て行ってしまう。
僕が昔一緒にバンドをしていたメンバーも来てくれる。ボーカルのシンジと、ベースのユウ。先週一緒に飲みにいったタカも来てくれる。僕らは顔をくっ付けあうようにして一言二言だけ会話を交わす。ボーカルのシンジだけは昔と変わらず長い髪をしていて、ユウはメンバーのなかで唯一結婚して子供もいる。すっかり良いお父さんという風貌になっている。
1バンド目の演奏が終わり、次のバンドの準備で会場が静かになるとタカが声をかけてくる。
「どうだ、出来のほうは?」とタカが言う。
「さあね」と僕は答える。「60%ぐらいじゃないかな」
「それだけあれば十分だろ。何事もほどほどにな」タカはそう言って笑う。
それからはみんな黙ってバンドの演奏を見ている。リエも戻ってきて、リエと同じような格好をした4人の友達を連れてくる。遠足にでもいくようにみんな仲良く同じバックを持っている。リエの彼氏は居場所がなくなったみたいで僕の近くに腰を下ろして黙って演奏を見ている。
3バンド目が終わるとリエと楽屋にいって準備をする。楽屋といっても鏡があるような立派なものではなく、楽器や機材を置くだけの物置のようなところだ。
「リエ、チョー緊張してきちゃった」とリエは言う。
一緒にライブをするのは4回目で、身内以外誰もいないんだから緊張することもないんだよ、と僕は言う。
「そんなこと言ったって」とリエは胸に手をあてて大きな息をする。
4バンド目が終わるとライブハウスの人から声がかかる。
「それじゃあ、行こうか」と僕は言う。
「うん」とリエは言って僕の手を握り僕を見つめる。彼氏が見たら殴りかかってくるかもしれない。
急いでステージにいってセッティングをする。機材を運んでたくさんのコードを繋ぎ合わせ、リハーサルで調整した目盛りに合わせる。その間リエは何をしていいのかわからないみたいにうろうろしているだけだ。コン、コン、とマイクを叩いて音が出るのを確認してから僕はリエに頷く。
「始めまして『マタハリ』です」リエは強張った声で客席に向かって言う。そして照れ笑いをして助けを求めるように僕を見る。
「今回でこのバンドは終わりなんだけど、一生懸命やります。よろしくお願いします」
リエがそういうような簡単な紹介をして、曲を始める。友人たちがパラパラと拍手をしてくれる。
演奏を始めるとただリズムに乗ってギターを弾く。余計なことは何も考えない。赤や青のライトが僕に当たり、その眩しさで客席はほとんど見えない。見えたところで客はほとんどいない。最前列のリエの友達がケータイのカメラを使って写真を撮っている。リエは身体を上下に揺すってふしぶしに歌を入れる。タイミングを計るためにときどき僕のほうを見る。僕はちょこちょこ機材を動かし、ギターを弾くことに専念する。僕もリズムに乗って楽しく演奏することができる。アパートで練習していたときよりも手応えを感じる。演奏が終わると僕とリエは「ありがとうございました」と言って客席にお辞儀をする。友人たちも含めて客席からパラパラと拍手が起こる。髪の長いシンジがピィーと口笛を鳴らす。僕は、まあこんなものかなと思う。
僕とタカ、シンジ、ユウ、リエとその彼氏、リエの友達4人、10人で打ち上げのために近くのチェーン店の居酒屋に行く。運よく大きなテーブルが空いていて、みんなで円を囲むようにして座敷の席に座ることができる。男たちはみんな生ビールを頼み、女の子たちはウーロン茶を頼む。乾杯をするとそれぞれに話し合い、いつの間にかグループはふたつに分かれてしまう。僕のとなりにはタカが座り、テーブルを挟んでリエと彼氏がいる。
「終わったらふたりで飲みにいこうぜ」とタカがこそこそと僕に言う。
「明日の仕事大丈夫なのか?」
「まあな、もう慣れてるから」
「リエから聞いたんスけど、仕事探してるんですか?」とリエの彼氏が僕に言う。
「そろそろ始めなくちゃいけないと思ってるんだけど」
「俺の仕事場ちょうど人探してるんですよ。良かったらどうッスか?肉体労働なんですけど、金は悪くないスよ」
「有り難いけど自分で探してみるよ。どうしようもなかったらそのときは頼むかもしれない」と僕は言う。
シンジとユウ、その他の女の子たちはシンジが中心になってワイワイと盛り上がっている。和やかな雰囲気だ。シンジは時々長い髪を掻きあげながら女の子をうまくリードしている。シンジは特にかっこいいというわけではないけど昔から女に不自由したことがなく、いつも3、4人の彼女のアパートを泊まり歩いているみたいだった。僕はどうやってそんな器用なことができるのかわからなかったけど、シンジは今でもろくに働かず路上で自作の歌を歌い、自分のアパートでマリファナを栽培している。
結構前のことになるけど、僕とタカとシンジの3人で飲みに行ったとき口論になってから、以前ほどシンジとは頻繁には会わなくなってしまった。シンガーソングライターのシンジは世界を救うのはラブ・アンド・ピースだけだ、おまえたちはなんにもわかっていないと言い切り、僕とタカはそれはそうかもしれないけど、もうジョンレノンもジミヘンも死んだんだからそういう時代ではないと反論した。お互い下らないこだわりから生まれた下らない喧嘩だとわかっていたけど、それから僕とタカのふたりだけで飲みにいくことが多くなった。
シンジは「どこ住んでんの?」とか「血液型なに?」とか、「それいただき、ゲッチュウ」とか、まあ、相変わらず調子のいいノリで女の子たちを笑わせている。
「ミュージシャンてのは、大変なのよ」とシンジは女の子に言っている。「本当に売れたいと思ったらオーディションとかに応募するときもさ、審査員が誰なのかってことを調べてその審査員が好みそうな曲を作らなくちゃいけないんだよね」
女の子たちは「へーえ」という反応をする。
「結局やりたいことやれないわけよ、俺たちはな、なあそうだろ?」シンジは僕に遠くから呼びかけて相槌を求める。僕は「そうかもね」と答える。
「そういえば昔みんなでバンド組んでたんでしょ? どんな名前だったの?」リエが僕に聞く。それにはシンジが答える。
「『ネオ・プラネット・アース』俺が考えたんだ。なかなかいいでしょ?」シンジはしゃがれた声でそう言う。シンジの独特のしゃがれた声はそれなりに味があって、当時のバンドはCDを出そうかというところまで来ていた。でも結局みんなやりたいものがばらばらでユウが結婚することをきっかけにバンドは解散してしまった。
「えー『マタハリ』のほうがいいよぉ」とリエは言う。
「さっきの話なんですけど、審査員に合わせて曲を作らなくちゃいけないって本当なんですか?」とリエの隣に座った女の子が言う。顔の作りは女の子の中でいちばん整っていてほっそりとした綺麗な子だけど、色気というものが全然感じられない。なぜかみんな僕のほう見て話かけてくるけど、答えるのは決まってシンジだ。
「それが社会ってもんなのよ。世間に認められるということは、お偉いさんがすべてを握ってるの。良いものを作るんじゃなくて、お偉いさんが気に入ってくれればいいの」
「それじゃあ、私たちのアイデンティティってものはどうなるんですか? 個人の主張ってそんな簡単でストイックなもので……」
その女の子がアイデンティティと言った瞬間に隣のタカが僕の顔を見てプッと笑いかける。僕は長年の付き合いなのでタカの言いたいことはわかるけど、タカが笑った姿を見た綺麗な女の子はそれが気に入らなかったみたいで、
「何笑ってるのよ?」と眉間に皴を寄せてタカに言う。
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。