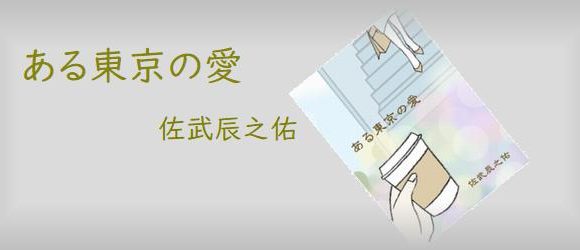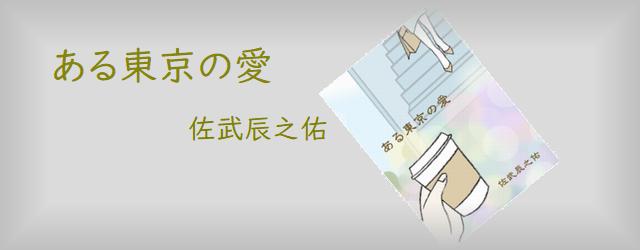
玄関のベルが何度も何度も鳴る。その音で僕は目を覚ます。もうひとりの僕が布団に寝たままのような眠気を引きずってドアを開ける。そこにはリエが立っている。
「寝てたの?」とリエは言う。
「悪い、今日は日曜だったね」と僕は言う。
「ちょっとまって」と僕はリエに言い、急いで布団を押入れに入れ、顔を洗って歯を磨く。その間リエは玄関で立ったまま待っている。
日曜はリエと練習することになっている。リエは20歳のアイドル顔をしたかわいい子で、僕がレストランのバイトに行ったときに知り合った子だった。リエは都会に出てきたはいいけど、これといってやりたいことが見つからずになんとなくバイトを続けているという感じだったので僕がメンバーに誘ったのだ。僕の作る音楽はボーカルがなくてリズムと電子音だけで作るものだったけどちょうど歌を入れるのも試してみたいと思ったので声をかけたのだ。リエは最初からあまり乗り気ではなかったけど、元々そんなに意思が強くないのでなんとかお願いしてやってもらうことになった。
音楽の趣味は全然合わなかったけどリエは若くて可愛かったから、それが何かの手がかりになるかとも思っていた。これも僕の試行錯誤のひとつだ。
ふたりでバンドを組んで半年ぐらい経った頃リエに念願の彼氏ができ、彼氏がバンドをやめろといったので来週のライブに一緒に出て僕とリエとの関係は終わることになっている。リエはジャンプしたらパンツが見えそうな短いオレンジのスカートに踵の高いブーツを履いてきている。豹柄のベルトをして彼氏に買ってもらったブランド物のバックを持っている。
「まあ入ってよ」と僕は言う。
リエは僕の部屋に入ってきて、テーブルを挟んだ向かい側に座る。
「いつまで寝てんの、もう昼過ぎじゃん」
「朝方まで曲作ってたんだよ。練習はしてきた?」
「してきたよ。来週本番だもんね。そういえば、バンドの名前どうすんの?今度も前と同じ?」
「『裸でエプロン』か。客受けしそうだと思ったんだけどな。だめだったね」
「リエ、もっと違うのがいいな。かっこいいやつ」
「じゃあ『ザ・レイパー・30分一本勝負・天上界からの断末魔』ってのは?リエの歌詞はダメェとか、ヤメテェとか、イクゥとかだけでいいし」
「今起きたばかりでしょ。どうしてそんなこと言うの。ケチョナルってカンジ」
リエは時々外国語のような、黒魔術のような単語を使う。僕はいいかげんそういうのにも慣れてしまったけど、最初は意志の疎通が難しかった。
「リエはね、もっとまじめなのがいいの!」と怒ったような顔をする。頬を膨らまして口を尖らせる。そういうわざとらしい表情をするのもどうかと僕は思うけど、本人は真面目みたいだ。
「真面目なのね、じゃあ『超懐疑人生的最終宇宙回帰論』ってのは?中国人もびっくりだ」
「どうしてそんなのしか出てこないの。やる気ないんじゃん?」
「あんまり名前のことについて考えたくないんだよ」と僕は言う。
「もう!リエが考えるから」リエはそう言うと、部屋の斜め上を見あげるようにして考える。目の周りにはキラキラと光る粉末をちりばめた化粧をしている。
「リエはね」とリエは言う。いちいち自分のことをリエと呼ぶことにも僕はどうかと思う。こういうふうにして僕は年をとってゆくことを感じるようになる。
「『リエリズム』ってどう?」
僕はため息をつく。
「リエリズムでもリエサルサでもなんでもいいよ。なんならリアルスティック・リエボンバーでも」
「そんじゃあね、『マタハリ』ってのどう?チョーいけてるってカンジじゃない?」
「マタハリってなんだ。マタマタなら知ってるけど」
「インドネシア語で太陽って意味だよ。チョーイイっしょ!」
僕は俯いて髪を掻き毟る。それでも、まあいいかと思う。どうせ今回で終わりなんだからと。
「とりあえず練習しようか」と僕は言う。
僕とリエは狭いアパートで近所に迷惑にならないように音を絞って練習する。リエは自作の英語の歌詞をリズムのふしぶしに入れる。日本語に訳すとあなたのことが好きなんだけど……とか、わかってあげられなくてごめんなさい……とか、私を理解しようとしないで、アハン、とかそんな感じだ。それについては僕もお願いしている立場なので文句は言わない。僕はもくもくと機材を動かし、ギターを弾く。
持ち曲の5曲を一通り流すと休憩する。僕はコンビニで買った紙パックのお茶を冷蔵庫から出してきてコップに入れてリエに勧める。
「私たちどうしてダメなのかな?」と一息ついたリエが言う。
「さあ、どうしてかな?」と僕は答える。
「結構いけてると思うんだけど、リエの友達に音源聞かせたらかっこいいって言ってたよ。なんかこう、もっとぉ、ライブの時もさ、一体感っていうのができたらいいんじゃない? お客さんと一緒にノリノリになってさ」
リエにしては珍しくまともなことを言う。僕はそう思うけど、どうしてか堅苦しいことを言ってしまう。
「一体感っていうのは、なんでもそうなんだけど、それを相手に与えようと思えば思うほどそれから遠ざかってゆくものなんだ。自然に吸い込まれてゆくっていうのがほんとの一体感だよ。欲望ってものに邪魔されて……」
「リエ、ワカンナイ。ゲンムラ、キッパロッチってカンジ」とリエは言う。
僕は辞書を開いて言葉の意味を探したくなるけどそれは残念ながら辞書には載っていない。
「そういえばお金あるの?そろそろ働かなくちゃだめなんじゃん?」
「あと10万ぐらいしかないね。来週のライブが終わったら仕事探さないとな」
そろそろカウントダウンだ。今回は4ヶ月自由な時間があった。僕は4ヶ月もひたすらゴミの
なかをさ迷い歩いていたのだ。
僕とリエはもう一度通しで曲をやってみて、それからセックスをする。リエの肌はふっくらして若々しいけど、そこにはまだ深みというものがない。彼女とのセックスのような遺伝子の情報交換をしているような圧倒的な一体感というものはない。リエからは頭が痛くなるような香水の匂いがする。僕はその中からリエ本来の匂いを嗅ぎ分ける。まだ開花されていないアンバランスな匂いと行き場のない無防備な生命力が僕を引き付ける。リエはシャワーを浴びると彼氏と待ち合わせがあるからと言って早々に帰ってしまう。
リエが帰ってしまうと急に時間を持て余してしまう。僕は練習しながら録音していた音を聞きなおし、少しずつ修正する。すでに曲の大筋は決まっているのでそこに細かい音を加えてみる。細部を削り取り、細部を加えてみる。でもそうやって全体的に良くなっているのか、悪くなっているのかは全くわからない。やればやるほどダメになっていくような気もするし、時間をかけたほうがいいような気もしてくる。ただ単に僕が曲を作り慣れていないだけなのか、バランスが悪いのか、頭が悪いのか、もっと根本的なものが間違っているのか、それすらもわからない。
印象派と呼ばれる画家たちはほんの数時間で、時には数十分で、歴史的な作品を一気に書き上げたという。そう考えると一瞬のひらめきを信じればいいような気がしてくるけど、パッと見た感じでは10分で仕上げた作品に実は何日も、何ヶ月もかかって描き出された作品もある。とにかくやってみて、前に進んでみて、それ以上その作品に対して意味を見出せなくなるまでやってみるしか方法はないのかもしれない。そう僕は思う。こればっかりは僕にはわからない。
僕がいつの日かヒット曲を生み出せればそれはわかるかもしれない。でもヒット曲を出したからといって、そのやり方でいつまでも続くわけはない。この世界では新しい無意味さが日々生まれてきていて、日々死んでいるのだ。前に進むためには壊し続けなくてはいけない。
今日は日曜日なので彼女からの連絡はない。彼女からの連絡がないということを寂しいと思う反面、日曜日は連絡が来ないとわかっているからどこかで楽な気持ちになれる。いつ来るかわからないものを待っているほどつらいものはないからだ。
僕は肉も野菜も入っていない焼きソバにマヨネーズをかけて食べ、それからもう一度曲の見直しをする。一歩も外に出ない一日は何も解決しないような気がするし、同じところをぐるぐると回っているような気にもなる。一日の経過もわからず、太陽の光も、月のなめらかな輝きも地球の回転も僕とは遠く離れたところにある。
一日があっけなく終わると月曜日がやってくる。月曜日は、週末をはさんだ平日は僕に重くのしかかる。彼女が夫とどんな週末を過ごし、そしてこの月曜日を彼女がどれくらい待っていたのか、僕はそういうことを知らず知らずのうちに考えるようになる。月曜日に彼女から連絡がこないのは拷問のようにも思える。一分、一分が、一秒の針が進むことさえ、時間というものが僕の身を鋭く抉り取るような気がする。
僕は目覚めるとすぐに布団の脇に置いておいたケータイを見る。そこに彼女からの着信の跡はない。迷惑メールが2通届いているだけだ。僕はのそのそと起き上がり、布団を押入れに入れ、顔を洗わず、歯も磨かずに彼女の言うまずいインスタントコーヒーを飲む。そして昨日作った曲を聞きなおす。僕は曲を聞きながら部屋のなかに置いてある機材を、ギターを見つめ、これらをバラバラにぶち壊すことができたらどんなにすっとするだろうと思う。インドにでも行ってさっさと人生を辞めてしまえばどんなに楽になれるだろうかと思う。いつもの、毎日繰りかえされる僕の目覚めだ。いくら砂を握り締めたところで、それは手から滑り落ちてゆく流動でしかないのだ。
「テーマは同じだ」“彼”が現れてそう言う。「曲を作ることや、歩くこと、仕事をすることも、オナニーをすることもすべては同じテーマなんだ。でもおまえは、どんなにやってみたところで、魂を削り取るぐらいがんばってみたところでゴミしか作れない」
「もういいよ。ほっといてくれ」と僕は言う。
「なにも親子同士の殺戮や、詐欺、精神異常、戦争や国際情勢、環境問題がここで問題なわけじゃない。そんなことじゃないんだ。ここじゃあ急に映画のような物語が始まるわけじゃない。進化がガンマ点に達してアルマゲドンがやってくるわけじゃない。特別な人間が特別なことをするわけでもない。とんでもないことが身に降りかかってくることが問題じゃない」“彼”は僕に指を突きつけてそう言う。
「ここでは、この街では、何も起こらないってことが問題なんだ。この下らない日常こそが蝕み、地獄からの鐘の音となってお前の耳に届くんだ。そうじゃないのか?」
僕はまた聞こえない振りをする。そして鼻から長いため息を吐き出す。そうしていつものように革命の卵は孵化しないまま時代の闇へと消えてゆく。
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。