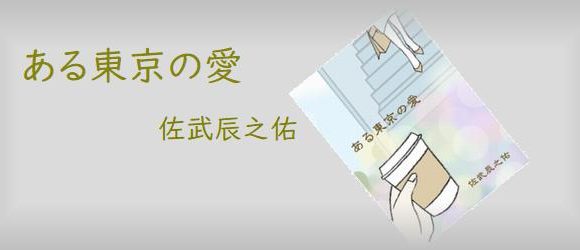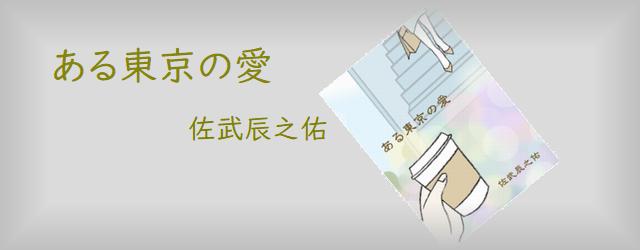
僕はほとんど彼女と会えずに、忙しい仕事に追われる日々を続ける。今月のノルマが目標に届かないから休日も出勤してくれないかと上司に言われ、人の出入りが頻繁に行われるので新しく入ってきた人には仕事を教えなくてはいけなくなる。僕も自分のノルマをこなすのに残業をしなくてはいけなくなる。僕はどんな無理な頼みごとを言われてもとにかくできるかぎりのことはやってみる。
仕事をするにあたって良いこともいくつかはある。休日の前の晩に飲むビールは格別においしいものになり、「彼」も全く姿を見せなくなってガミガミと言われることもない。でも取り立てて言えることといえばそれぐらいしかない。僕は少しずつお金を貯めていき、また元の生活に戻り、曲を作りながら平日の昼間に彼女と会えることを楽しみに過ごしてゆく。
物事はいつもとてもとても静かなところから始まる。我々が気付くことができないぐらいものすごく静かなところから。そこにはまだ色もなく、音もなく、形さえ、時間さえもない。そういうところから物事は始まる。しかしほんの僅かな小さなものが、いろいろな場所を潜り抜け、時間の壁を超え、多くのものを巻き込んで目の前に現れる。ある日突然、想像さえしていなかった死角から飛び掛ってくる。そうなったら……、いや、それは元々避けることができないのかもしれない。
いつものように僕は仕事に向かう。朝起きて、電車に乗り、電車に乗った瞬間から早く目的地に着かないかと考え始める。そんないつも通りの一日の始まりだ。各駅に電車が停まるたびに次はどこの駅なのかと掲示板で見てしまう。見なくても次がどこの駅なのかはわかっているけど、ついつい見てしまう。満員のエレベーターでも知らず知らずのうちに階数を示す数字を見つめてしまうみたいに。
会社に行って電話機の前に座ると、早く仕事が終わらないかと思い始める。いつも通りの一日だ。僕は仕事を始めてすっかりこちら側に馴染んでいる。人間関係も落ち着いてきて、仕事上なにをすればいいのか、なにをやってはいけないのか、そうゆうことも人に聞かなくてもだいたいわかるようになる。最初の頃は受話器の上げ下げで腕が筋肉痛になっていたけど、そういうことも今ではない。朝仕事が始まるととにかくお昼のチャイムが鳴るのを目指して電話をする。昼休みになると、社員食堂で昼食を食べ、休憩室で煙草を吸い、午後から出かける営業マンと午前中にアポイントが取れたお客さんの詳しい話をして一時間が過ぎる。なんだかバタバタしたまま終わってしまうけど、それでも昼休みは待ち遠しい。
昼休みにケータイを見てみると彼女から着信がある。彼女とのやりとりはほとんどがメールなので僕は不思議に思う。いつもとは違う何かが起こったときに毎回思うように、それは何かの暗示であるように思う。その暗示はプラスかマイナスのどちらかに進む。誰かにとってプラスのことが、別の人にとってはマイナスに働く。でも僕に起こることは大抵マイナスのような気がしてくる。だからその彼女からの着信は、僕を少し不安にさせる。
のんびりと電話をしている時間がないので僕は彼女にメールを送っておく。
「何かあった? 今日は仕事だよ」と。
3時の休憩のときにケータイを見てみても彼女からの連絡は入っていない。仕事が終わっても、アパートに戻っても彼女からの連絡はこない。僕は眠る前の布団のなかでいろいろと考えてしまう。考えれば考えるほど、不安の影は濃くなってゆくように思える。
次の日の昼休みにケータイを見るとまた彼女からの着信がある。僕は昼食を食べる前に休憩室に行って彼女に電話をしてみることにする。休憩室には飲み物用の自動販売機が置いてあり、壁に沿ってパイプ椅子が並んでいる。換気扇がうなりをあげて回っているけど、長年人々が煙草を吸ってきたせいで白い壁は薄茶色に変色している。僕はまだ誰もいない休憩室の椅子に座って彼女のケータイにかけて
みる。2回コールしただけで彼女は電話に出る。
「もしもし、元気?」と僕は言う。
「元気よ。そっちは?」と彼女。なんだかいつもよりも声が低いみたいだ。
「こっちは元気だけど、なんだか元気ないみたいだね?なにかあった?」
「うん」と彼女は小さい声で言う。
「どうしたの?」なんとなく時間の進むスピードが遅くなってゆくような気がする。
「ねえ」と彼女は言う。でもそれっきり黙ってしまう。僕はケータイをさらに耳にぴったりとつけて彼女の次の言葉を待つ。でも彼女は何も言わない。
「何かあった?背後霊でも見えちゃった?」僕がそう言っても彼女はクスリとも笑ってくれない。
「ねえ、もし……。もし……なんだけど……」彼女はそう言う。でもなかなか次の言葉が出てこない。僕は辛抱強く待つことにする。
「もしよ……。もしかしてって、ことなんだけど……」
「うん」と僕は答える。
「私が妊娠したって言ったら、どうする?」彼女はそう言う。
僕はなぜだか、そうだろうな、と思っていた。それ以外の選択肢は他になかったように思えてくる。僕は言葉に詰まる。
「ねえ、もしって、ことよ。聞いてるの?」彼女の言葉のスピードが上がる。
「うん、聞いてるよ」
「まだわからないんだけど、もしかしてってこと」
「うん」
「まだお医者さんに行ったわけじゃないの。そうじゃない可能性もあるんだけど…」
「うん」
「急に思い返してみたら、そうかもしれないって思っただけなの。そうじゃないかもしれないんだけど…」
「うん」
「どうかしら?」
彼女は僕に聞く。僕は、どうかしら、と言われても答えようがない。
「ねえ、聞いてるの?」
「聞いてるよ。でもどうかしらって言われてもしょうがないだろ」
今度は彼女のほうが黙ってしまう。
僕の耳には休憩室の換気扇が回る音が響いてくる。地球は回り続けているんだろうけど、時間は止まってしまったように思える。しばらくそのままでいるとケータイから彼女の泣く声が聞こえてくる。僕が彼女の泣く声を聞くのはこれが初めてだ。僕はケータイを耳に当てたまま、彼女の泣き声を聞いている。できれば彼女のところにいって、涙を拭いてあげたいと思う。頬に手を当て、目の淵を指でなぞり、キスをしたいと思う。でも僕は煙草臭い休憩室にいて、ケータイを耳に当てたままパイプの椅子に座っている。
「私」彼女は泣きながら、言葉に詰まりながらそう言う。「どうすればいいと思う?」
「近いうちに一度会おうか。僕から連絡するよ」
「うん」と彼女は言う。彼女はまだ泣いている。
「待ってるわ」
「元気でね」
「うん。ねえ、ごめんなさい」と彼女は言う。
僕はしばらく「ごめんなさい」について考える。
「べつに謝ることじゃないよ」
「うん」
「今日は……火曜日だから、次の休みの金曜日には時間が空くと思う」
「うん」
「それじゃあね、元気でね」
「うん」
僕はできればこのまま電話を切りたくないと思う。できれば彼女が泣き止んで、気持ちが落ち着くまで。僕はもっと彼女に何かを言うべきなのだと思う。何かをいい忘れているような気がする。
食事を終えた同僚の男が休憩室に入ってくる。
僕は「じゃあね」と言って、電話を切るボタンを押す。
同僚は僕がいるのをちらっと見てから自動販売機にコインを入れ、ボタンを押す。ガタンという大きな音がして、ジュースが出口に出てくる。同僚はジュースを取り出すと当たり前のように僕の隣の椅子に座る。それから煙草を取り出し、火を点け、ジュースを何度か振ってから、蓋を開ける。プシュという音が僕の耳に入る。
「あーあー、だるいなあ」と同僚が言う。同僚は僕に何かを求めているのがわかる。僕が何かを言うのを待っているのがわかる。でも僕は何も言わない。
「おい、おまえどうしたんだよ? 顔が死んでるぞ」僕の顔を見た同僚は驚いたように言う。
「ああ」
「どうしたんだよ。嫌な客でもいたのか?」
「ああ」
「なんだよ、らしくねえじゃねえか」同僚は僕の身体を押す。
僕はバランスを崩して椅子から落ちそうになる。僕は急にこの同僚に対して猛烈な怒りがこみ上げてくるのを感じる。それは大地から、空から、この街の隅々から湧き上がってくるように思える。
僕は目を閉じて自分の瞼に映る血の色を見る。僕の身体を流れるその色は赤黒く、旗のように風に靡いている。僕はこのまま自分の血の中に溶けていって大空に舞い上がり、空を飛べたらどんなに気持ちがいいだろうと思う。僕を考えさせるものは何もなく、翼を広げて空とひとつになる。見渡す限りの地平線が僕を囲み、眩しい太陽の光に目を痛める。僕の下に見える大地からは纏わりつくような血の匂いがする。木々たちはその血を吸い込み恐怖で怯えているのがわかる。僕はもうそんなところには戻りたくないと思う。
「大丈夫、ちょっと気分が悪かっただけだよ」僕は目を開けて同僚に言う。なんとかいつも通りの笑顔を作ろうとする。
「マジで大丈夫かよ? なんなら医者いったほうがいいんじゃん?」同僚はそう言ってくれる。同僚の表情からは本当に僕を気遣ってくれていることがわかる。
そう、それは同僚のせいではないし、責任でもない。ただ彼らに僕のデーターベースがないだけだ。データベースがないだけだ。
「今日は帰ったほうがいいんじゃねえか? 具合が悪かったってチーフには言っとくからさ」
「いや、大丈夫だよ。仕事がしたいんだ」
僕はそう言う。こんな状態でアパートに戻ったところでいろんなことを考えてしまって、余計に落ち込んでしまう。
「無理しねえほうがいいぞ。おまえはがんばってるんだからな」同僚はそう言ってくれる。
僕はなんとか笑ってみようとする。でもうまく笑えない。
同僚はそれ以上何も言わずジュースを飲み、煙草を吸っていた。僕は昼休みが終わるまで自動販売機のコインの投入口の小さな穴をじっと見つめていた。
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。