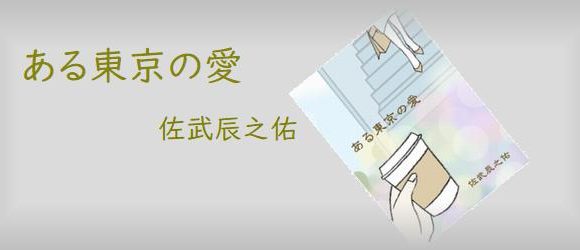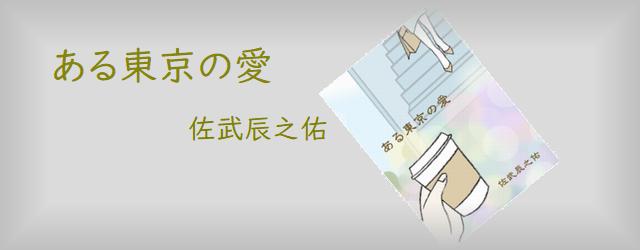
僕はアパートに戻ると書類の入ったビジネスバッグを机の上に放り投げ、忌まわしい求人誌をほんとは火でも点けて燃やしたいけどゴミ箱に入れ、スーツを脱いで部屋に寝転ぶ。いつもの、僕の生活の匂いが染み付いた見慣れた天井がある。でもその天井は昨日までとは違う角度から僕を見下ろしているように思える。満員電車で押し付けられる他人の皮膚のように僕を落ち着かせなくさせる。こんなふうにして僕の仕事は始まる。
僕は次の日からテレフォン・アポインターの仕事を始める。広々としたフロアにはぎっしりと机が並べられ、ひとりひとり仕切られたボックスの席にすわってひたすら電話をかける。何十人も一斉に電話をかけている光景は遠くからみるといかがわしい宗教行為のように見えなくもない。僕も信者のひとりになって配られてきたリストの順番に電話をかける。
「お忙しいところ申し訳ありません、こちら○○社と申しますが、ただいまキャンペーンを致しておりまして……」
これと全く同じ台詞が、違う声のトーンと音域でフロア中に響き渡る。まだ電話が発明されていなかった時代の人が見たら、みんなで悪魔でも召喚しているかのように思うだろう。僕もとにかく電話をかける。そのうちにリストにある電話番号をみただけで指が勝手に番号を押してしまうようになる。
だいたいは「お忙しいところ申し訳ありません」の最初のワンフレーズを言っただけで、電話の向こうの相手が凍り付いているのがわかる。僕だってそんな電話をとってしまったらすぐに受話器を置きたくなるのはわからないでもない。そこで無言で切られるのはまだましなほうで、さんざん文句を言われるときもあれば、一日中頭から離れないような強烈なことを言われることもある。そうすると僕は傷つく。でもどんなに傷ついたところで、傷を眺めていてもどうにもならない。とにかく僕は指を動かす。何かを考える前に僕は指を動かし、発信音に耳を傾ける。
僕はもし生まれ変わったらもう電話のある時代には生まれたくないというぐらい毎日毎日電話をすることになる。一日中他人に電話をしているとどんなに人々の心が乾いているかということがわかる。番号通知しないとかからないことはしょっちゅうだし、今まで話をしていたのに急に留守番電話のメッセージに切り替わることもある。一日に電話をかけなくてはいけないノルマは150件以上で、もしアポイントが取れて営業マンに引き継ぐことができたら一件につき50円のインセンティブがもらえる。
どんな仕事だろうがそれは仕事であり、下らないことは変わらない。この下らなさから、このシステムから、このゴミの山から逃れることはできない。でも僕は一生懸命仕事をする。とにかく最初の3週間は誰よりも熱心に仕事をする。必要があれば仕事をアパートに持ち帰り、覚えなくてはいけないことは片っ端から頭に叩き込む。休みも取らない。休日を返上しても、お金が貰えなくても僕はとにかく仕事をする。そして仕事の成績はトップを目指す。そして会社の同僚にはできるだけ明るく接し、冗談を言ってみんなを笑わせる。上司の人もそんな僕を認めてくれて、頼りにさえしてくれるようになる。積極的に同僚を飲みに誘う。
僕の持ちうるすべての能力を使って僕は社会と自分とのズレを矯正してゆく。どこかがへっこんだら裏側からガン、ガンと叩き、膨れ上がったらこちら側からガン、ガンと叩く。とにかく最初が肝心なのだ。仕事もできなくて煮え切らない哲学者みたいな顔をしていても誰も相手にしてくれない。貝のように閉じこもっていたらそれは彼らにとっては格好の的なのだ。殻が割れるのもお構いなしに、彼らは僕を小突く。そうすると僕はさらに殻を硬くしなくてはいけなくなる。そうすると彼らはもっと強い力で突いてくる。僕はさらに殻を硬くする。
仕事を一生懸命することによって僕はぐいぐいと彼らのなかに入ってゆき、自分がいちばん楽なポジションを獲得する。そうすれば上司にネチネチ言われることもないし、下らないことを考えさせられることも少なくなる。最初から端っこのポジションに陣取って、ある日突然ポジションを変えようと思ってもそれは非常に難しい。彼らの僕に対するイメージが固まってしまったらもう手遅れだ。ある日突然僕が変わろうと思っても、彼らはわざわざ新しい目で僕を見てくれることはない。彼らの頭の中は同じところをぐるぐると回っていて、その回転の外にあるものに目を向けようとはしない。
だから僕は一生懸命仕事をする。ある程度の時期が過ぎれば彼らの僕に対するイメージも固まってきて、僕はその場所でふわふわと浮いていればいいのだ。かといって僕が抱え込むストレスが減るわけじゃない。僕は理科室のホルマリン漬けのように頭の先までしっかりとストレス漬けになってしまう。僕なんかを漬け込んでもまともなダシなんて採れないけど……。
僕は働いている間は曲作りをしないことにしている。僕は二つのことを同時に集中してできるほど器用じゃないし、それに彼らの間に埋もれていてまともなものが作れるはずもない。僕は曲を作る機材を押入れにしまい、扉を閉める。ひとまず夢の向こう側にすべてを置いてくる。
一ヶ月、二ヶ月もすると僕も彼らに対して、彼らも僕に対して心を許せるようになってくる。アルバムに収められた美しい青春の一ページのようになる。そうやって僕は太陽からも月からも離れた期間をやりすごしてゆく。でも彼らに対して慣れ親しんでくればくるほど僕はだんだんとかぐや姫の気分がわかってくるようになる。
「こちら側にも素晴らしいことはたくさんあって本当に名残惜しいんだけど、どうしても私は月へ帰らなくてはいけないのです」というふうに。
仕事を始めたことでいちばん悩むのは彼女のことだ。テレフォン・アポインターの仕事は休日が不規則なため彼女と会えることはめったにない。週に一度か二度メールをやりとりするだけだ。僕の休日といっても掃除をし、洗濯をし、ご飯を作って食べて、買い物に行って、お風呂に入って音楽を聴いていると一日なんてあっという間に終わってしまう。電球が切れたら電気屋に行かなくてはいけなくなるし、ティッシュペーパーがなくなればドラッグストアーに行かなくてはいけなくなる。
彼女も夫から頼まれごとを言われることもあるし、学生時代からの品のいい友人のお茶会なんかにいっていたらだらだらと一日が終わってしまう。僕とはなかなか噛み合わなくなる。
僕は毎晩布団に入ったときや、休日の朝目覚めたばかりのときに彼女のことを考える。彼女の生活を思い描き、彼女の夫が彼女を抱いているところを想像する。その想像は日増しに本当の出来事のように思えてくる。風が吹き、土を運び、そこに雨が降って地面が固まってゆくようにそれは想像というよりもしっかりとした物語のようになってしまう。僕は毎晩のように、擦り切れたリモコンの再生ボタンを押すように、その物語をさらに踏み固めてゆく。それはいつも夫が夜遅くに玄関のドアを開けるところから始まる。
夫がドアを開けた音で彼女は玄関に出てゆく。夫は疲れた顔をしてビジネスバックを彼女に手渡し、廊下を抜けてリビングに向かう。夫はスーツを脱ぎ捨て、ワイシャツとパンツだけの姿になってソファに座る。彼女は夫が脱ぎ捨てたスーツを拾い、寝室のクローゼットに行って皴にならないようにきちんと裾をそろえてハンガーにかける。彼女がリビングに行くと、
「おい、飯」と夫は言う。
彼女は作っておいた晩御飯をレンジで温め、キッチンのテーブルに運ぶ。スープを温めなおし、お盆に載せてビールとコップもテーブルに運ぶ。夫は黙ってご飯を食べ始める。おいしいともありがとうとも言わない。夫が点けっぱなしにしてあるテレビの音がキッチンにも聞こえてくる。彼女もキッチンのテーブルに座る。でも夫は一言も口をきかない。夫はいつも僕が座る席に座っている。
僕が彼女のマンションに行くとよく彼女はご飯を作ってくれる。彼女の得意な料理はオムライスや、カレーなど以外に庶民的なものだ。でもオムライスといっても上質なオリーブオイルがケチャップご飯に程よく絡めてあり、基本的な味はバターとワイン、コンソメで調えてあり、そこにふわふわの卵が乗せてあるのだ。どこかの洋食屋で出てきてもおかしくないぐらいそのオムライスはおいしい。僕にとってはそのオムライスは幸せの象徴と呼んでもいいぐらいだ。僕は自分が感じたままにそんなことを彼女に言う。彼女は照れて笑い、「そんなことないわよ」と言いながら嬉しそうな顔をしてくれる。
でも夫は、たとえそのオムライスが出てきたとしても何もいわない。まずいとも、おいしいとも、今日は味にもう一工夫したんだね、とも言わない。いただきますとも言わず、ごちそうさまとも言わずに夫は食事を終えるとリビングにビールとコップを持って移動してしまう。
彼女は夫が食べ終えた食器をキッチンで洗い、よく拭いてから元にあった棚に並べる。彼女はヨーロッパあたりの重量感のある、繊細なデザインの食器が好きなのだ。デパートなんかに行くとついつい買ってしまう。お気に入りのコーヒーカップを大事に扱い、イタリアから輸入したコーヒーメーカーとミネラルウォーターでひとりのティータイムを楽しむ。夫が勝手に自分のカップを使うときがあるけど、彼女は文句を言わない。
食器の片づけが終わると彼女はお風呂のお湯を落とし、お湯を落としながら明日夫が会社に来てゆく服の準備をする。夫は書斎に移動していて、書斎の扉からは高級ステレオから流れるクラシックが聞こえる。彼女は書斎のドアをノックして、返事があるのを待ってから音を立てないようにドアを開ける。そして明日着てゆく服の色を確認する。スーツの色は、ネクタイの色は、ワイシャツの色は、といった具合に。
夫がお風呂に入ると彼女は脱衣所に夫のパジャマを置いておく。彼女は入れ代わりにお風呂に入る。髪と身体を洗い、バスタブにこびり付いた汗と垢をスポンジで磨く。お風呂から上がると彼女はパジャマを着て、夫の書斎にあるビールの缶とコップを片付け、キッチンを洗ってから、電気を消す。
彼女が寝室のドアを開けるともう中は真っ暗になっている。分厚いカーテンのおかげで部屋のなかは完全な暗闇になっている。彼女は足音を立てないようにしながら、手探りでベッドの奥へと進む。注意を払いながら掛け布団の中に身体を滑り込ませる。
夫は彼女が来るのを待ち構えていたかのように擦り寄ってくる。夫は掛け布団を横にずらし、彼女に覆いかぶさる。ゴキブリの羽のような脂っこい手で彼女の身体に触れる。夫は彼女のパジャマも脱がさずに前のボタンだけを外し、生臭い口臭がする口で彼女の乳首を舐める。彼女はどうすることもできない。断れる理由も見当たらない。夫は彼女のパジャマのズボンとパンツを膝まで下ろすと、彼女の中に入ってくる。夫は身体を揺するたびに虫のようなギィー、ギィーという声を出す。たった5分かそこらでそれは終わってしまう。
夫は何事もなかったかのように自分の居場所に戻ってゆき、しばらくすると規則正しい寝息が聞こえてくる。
彼女は自分のパジャマを元通りに直し、しばらくは眠れないまま暗闇の中でじっとしている。そのまま運よく眠れることもあるけど、だいたいは寝室を出てキッチンに向かう。夫が完全に眠ったのを見計らってから。
彼女はキッチンの小さな明かりをひとつだけ灯し、テーブルの椅子に腰掛ける。高級マンションの密閉された防音効果のおかげで周囲の音は何も聞こえない。椅子が床を引きずる音、彼女が椅子に座る音、テーブルに手を置いたときの音、そういった音のひとつひとつはとても印象的な出来事であるように彼女の耳に響いてくる。彼女はテーブルにうつ伏せになって泣く。声も出さずに、自然に涙が出てくるというような泣き方だ。彼女の性器には夫が入ってきたヒリヒリとした感触が残っている。でも彼女はどうして自分が泣いているのかよくわからない。僕への罪悪感でもないし、この生活になにか不満があるというわけでもない。彼女は自分がどれだけ恵まれた環境にいるのかということがわからないわけではないし、この世の中から見れば、自分は幸せな部類に入るだろうということもわかる。でも彼女は涙を流す。どうしていいのか、どうすればここから抜け出せるのか、そんなことを考えることは随分昔に諦めてしまった。それでも彼女は冷たい涙を流し続ける。パジャマの裾が濡れて、着替えなくてはいけないぐらいに。
ある程度気分が落ち着いてくると彼女は眠ることに決め、寝室に戻る。明日の朝もカーテンを開け、夫を起こし、ご飯を食べさせ、彼女なりの精一杯の笑顔で見送ってあげなくてはいけないからだ。そうして彼女はまた暗闇のなかに戻り、夢の中へと堕ちてゆく。
気が付くとこのような物語は勝手に僕の頭のなかで再生されている。誰かが忍び寄ってきて僕の頭のなかにある再生ボタンを押すのだ。そのときどきによっていろんな物語が再生される。あらゆる可能性を想定され、あらゆるシーンが再生される。夫はたまに早く帰ってくると、何度も何度も、怒りをぶつけるかのように彼女を抱くときもあれば、彼女のほうから夫を求める場合もある。彼女が僕を求めてくれるバージョンもある。でもその物語はうまく再生できない。記憶を再生するためのソフトは傷がついてしまっていて、僕のはずが夫になったり、全く知らない誰かになったりする。
《佐武辰之佑/プロフィール》
1976年生まれ。富山県高岡市出身。英米文学科卒業後、海外放浪を始め、同時に小説などの執筆活動を始める。 2007年よりイタリア・ミラノ在住。フリーライター、フォトグラファーとして雑誌やWEBサイトに記事を投稿。イタリア・ミラノの観光情報サイト「ミランフォ」運営者、各コーディネートも承っています。続きをご覧になりたい方はKindle小説『ある東京の愛』へアクセスしてください。ホームページにて委細がご覧いただけます。